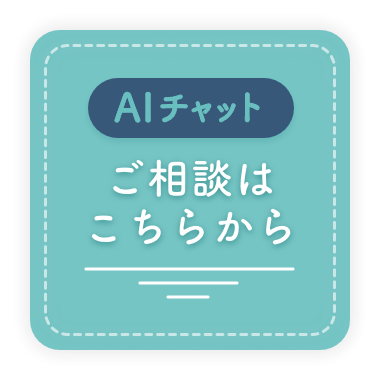2025年10月29日
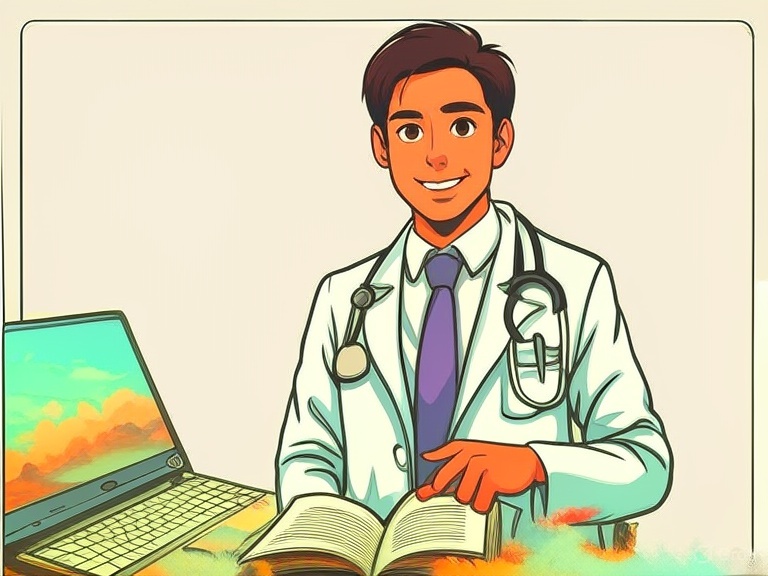
大人の発達障害とは?見逃されがちな特性の全体像
発達障害は、生まれつきの脳の働き方の違いによるものです。子どもの頃から特性はありますが、大人になってから気づくケースも少なくありません。
他人とのコミュニケーションが苦手、場の空気が読めない、遅刻や忘れ物が多いなど、日常生活でさまざまな「生きづらさ」を感じていませんか?
これらの特性は本人の努力不足や育て方が原因ではなく、脳機能の発達がアンバランスであるために起こるものです。環境との相互作用によって、欠点にも長所にもなり得る特性なのです。
大人の発達障害で多いのは、自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠如・多動症(ADHD)です。これらは単独で現れることもあれば、複数の特性を併せ持つこともあります。
発達障害の特性はとても多様で、その診断には「明確な線引き」をつけにくいところがあります。いわゆる”グレーゾーン”が大きいのが特徴です。
なぜ大人になって発達障害に気づくのか?
子どもの頃は周囲のサポートがあり、特性が個性として捉えられていたため、本人も周囲も気づかずに成長することがあります。
しかし、進学や就職で社会に出ると、人間関係は複雑になり、様々な人とコミュニケーションをとることが求められます。相手の表情から意図を察したり、周囲に合わせて行動したり、仕事を計画的に進めるなど、社会性が要求されるようになります。
このとき、潜在的に持っていた発達障害の特性が表面化し、人間関係や仕事でつまずいてしまうことがあるのです。そして、そのときに初めて発達障害に気づくケースが少なくありません。
私が診療している患者さんの中にも、40代、50代になって初めて自分の特性に気づく方が数多くいらっしゃいます。
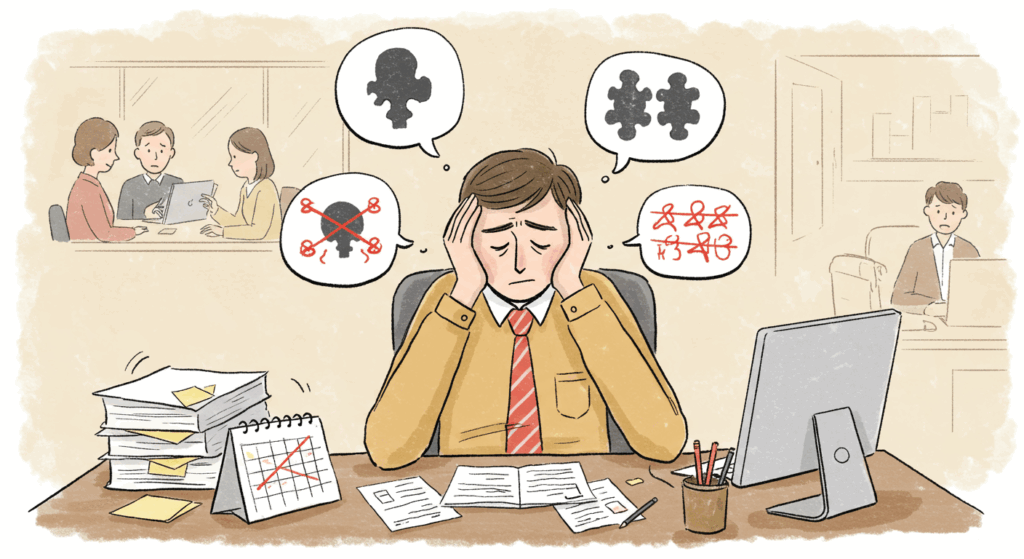
特に2004年の発達障害者支援法施行以前に学校教育を受けた世代では、発達障害の認知度が低く、「努力不足」「怠け」などと誤解されてきた方も多いのです。
現在でも、コロナ禍で支援の窓口を訪れたことをきっかけに自分の障害に気づくケースが相次いでいます。
自閉スペクトラム症(ASD)の特徴と見逃されやすいポイント
自閉スペクトラム症(ASD)は、以前はアスペルガー症候群や自閉症と呼ばれていたものを包括した概念です。「スペクトラム(連続体)」という言葉が示すように、特性の現れ方には幅広い個人差があります。
ASDの主な特徴
ASDの特性は主に以下の2つに分けられます。
- 社会的コミュニケーションや対人関係の困難さ
- 限定された反復的な行動パターン(こだわりの強さ)
社会的コミュニケーションの困難さは、他人の気持ちを察することが難しいという特性から生じます。これは「メタ認知」、つまり自分を客観的に捉える力の困難さが根本にあると考えられています。
こだわりの強さは、想定外の出来事に対応できず不安になるため、自分が作ったルールや生活パターンを守ることに執着する形で現れます。
大人のASDで見逃されやすいポイント
大人のASDは、知的能力が高い場合や、社会的なスキルを学習によって身につけている場合に見逃されやすくなります。特に以下のような特徴が見られることがあります:
- 悪気はないのに、言動によって相手を怒らせてしまう
- 相手の表情や身振りから気持ちを汲み取れない
- 興味のある分野の話になると夢中になって話し続ける
- 相手と会話がかみ合わない、一方的なコミュニケーション
- 面接が苦手で就職活動がうまくいかない
- 指示が曖昧な仕事の対応ができない
- 臨機応変に業務ができない
- 複数の業務を並行して取り組むことができない
一方で、ASDの特性は強みにもなります。ルールを守る真面目さや細やかさ、行動に裏表がなく誠実、視覚的(または聴覚的)な記憶力が優れている、特定分野に関する知識が豊富、一つのことをコツコツと集中して行うことができるなどの長所があります。
注意欠如・多動症(ADHD)の特徴と見逃されやすいポイント
注意欠如・多動症(ADHD)の中心にあるのは、注意力を持続できないという特性です。そのために不注意や多動が生じ、理性で欲望を抑えられず衝動的に行動してしまうことがあります。
ADHDの主な特徴
ADHDの特性は主に以下の3つに分けられます。
- 不注意(注意を持続することが難しい)
- 多動性(じっとしていられない)
- 衝動性(考える前に行動してしまう)
これらの特性は、注意欠如優勢型、多動性・衝動性優勢型、混合型の3つのタイプに分類されます。大人のADHDでは、多動性は目立たなくなり、不注意の症状が前面に出ることが多いです。
大人のADHDで見逃されやすいポイント
大人のADHDは、子どもの頃とは異なる形で現れることがあります。特に以下のような特徴が日常生活で見られることがあります:
- 整理整頓が苦手で、物をよく失くす
- 集中ができず、ケアレスミスが多い
- 忘れ物や落とし物、遅刻が多い
- 計画を立てるのが苦手で、締め切りに間に合わない
- じっと座っていられず、常に何かをいじっている
- 順番を待つのが苦手で、会話に割り込んでしまう
- 考えるよりも先に行動してしまう
- 感情のコントロールが難しく、イライラしやすい
私の臨床経験では、大人のADHDは「時間の管理」「物の管理」「感情の管理」の3つの管理が難しいという特徴があります。

ADHDの特性も強みになることがあります。創造性が高い、直感的な判断が得意、複数の視点から物事を見ることができる、エネルギッシュで行動力がある、危機対応能力が高いなどの長所があります。
あなたは自分の特性に心当たりがありますか?
限局性学習障害(LD)と感覚過敏について
発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)以外にも、限局性学習障害(LD)があります。また、感覚過敏も発達障害と関連する重要な特性です。
限局性学習障害(LD)の特徴
限局性学習障害(LD)は、知的発達に遅れはないにもかかわらず、読む(読字障害)、書く(書字障害)、計算する(算数障害)などの特定の能力が著しく低い状態を指します。
代表的な学習障害であるディスクレシア(読字障害)では、文字が記号のように見える、ぐにゃぐにゃと動いているように見えるなど、文字を文字として認識できないため、内容を理解することや書くことが難しくなります。
大人になると、読み書きや計算の困難さを様々な方法で補償するようになるため、表面上は目立たなくなることがあります。しかし、新しい環境や状況ではその困難さが再び表面化することがあります。
感覚過敏について
発達障害、特に自閉スペクトラム症(ASD)の方には、感覚過敏が見られることがあります。これは特定の感覚刺激に対して、通常よりも強く反応してしまう特性です。
- 視覚過敏:蛍光灯のちらつきや強い光がまぶしく感じる
- 聴覚過敏:日常の音(電車の音、人の話し声など)が大きく感じる
- 触覚過敏:特定の素材の服が着られない、タグが気になる
- 嗅覚過敏:わずかな匂いに強く反応する
- 味覚過敏:食べ物の好き嫌いが激しい
これらの感覚過敏は、日常生活や社会生活に大きな影響を与えることがあります。例えば、オフィスの蛍光灯の光や音が気になって仕事に集中できない、特定の素材の制服が着られずに職場で困るなどの問題が生じることがあります。
一方で、感覚の鋭さを活かして、他の人が気づかない細かな変化に気づく能力として発揮されることもあります。
発達障害の診断はどのように行われるのか?
発達障害の特性や困りごとは人によって異なり、外見からは判断できません。そのため、医療機関での診察・診断は、それぞれの特性・困りごとを丁寧に聞き取ることから始まります。
診断までの流れ
発達障害の診断は、精神科や心療内科など、発達障害を専門とする医師に判断してもらうことが必要です。診断の流れは一般的に以下のようになります。
- 問診:医師が今困っていることや子どものころからこれまでの生活などについて本人や家族から情報を聞き取ります
- 心理検査:必要に応じて発達検査、知能検査、人格検査などを行います
- その他の検査:認知機能検査や画像検査、脳波の測定、IQの測定などが行われることもあります
- 総合的判断:これらの情報を診断ガイドラインの基準に沿って検討し、発達障害と診断されるかどうか判断されます
準備しておくと役立つ情報としては、困りごとやこれまでの経過をメモしたもの、母子手帳や小学校の通知表などがあります。これらを持参すると診断の参考になります。
診断を受けるメリット
発達障害の診断を受けることで、以下のようなメリットがあります。
- 自分の特性を理解し、適切な対処法を見つけることができる
- 周囲の人に自分の特性を説明しやすくなる
- 必要に応じて合理的配慮を受けられる可能性がある
- 就労支援などの福祉サービスを利用できる可能性がある
- 二次障害(うつ病や不安障害など)の予防や治療につながる
発達障害の診断は、レッテル貼りをするためのものではありません。診断を受けることが出発点となり、困りごとへの改善策を見つけ、将来の選択肢を増やすことにつながります。
診断名は、自分自身の特性を深く理解したり、幸せになるために必要なサポートを得るための手段として存在しています。仕事や生活の中で生きづらさを感じていて「もしかしたら発達障害かもしれない」と心配になった時には、ひとりで悩むことなく、まずは医療機関を受診してみることをお勧めします。
発達障害の方への支援と治療アプローチ
発達障害の治療・支援は、薬物療法、精神療法、環境調整など多角的なアプローチが必要です。それぞれの特性や困りごとに合わせた個別の支援が重要になります。
薬物療法
ADHDに対しては、注意力や衝動性をコントロールするための薬物療法が有効な場合があります。日本では、メチルフェニデート(コンサータ®)やアトモキセチン(ストラテラ®)、グアンファシン(インチュニブ®)などが承認されています。
ASDに対する中核症状を改善する薬はありませんが、併存する不安や抑うつ、睡眠の問題などに対して薬物療法が行われることがあります。
精神療法・認知行動療法
発達障害の方には、以下のような心理的アプローチが有効な場合があります。
- 認知行動療法:考え方のパターンや行動を変えることで症状の改善を目指す
- ソーシャルスキルトレーニング:対人関係のスキルを学ぶ
- 心理教育:自分の特性について理解を深める
当院では、公認心理士、臨床心理士の資格を持った専門スタッフがカウンセリングを行い、薬物療法だけに頼らない治療を提供しています。
環境調整と合理的配慮
発達障害の方が力を発揮するためには、特性に合わせた環境調整が重要です。職場や学校での合理的配慮としては、以下のようなものがあります。
- 指示を明確に、できれば視覚的に伝える
- 一度に複数の作業を与えない
- 静かな環境で作業できるようにする
- スケジュール管理のためのツールを活用する
- 感覚過敏に配慮する(照明、音など)
これらの配慮は、発達障害の方だけでなく、すべての人にとって働きやすい環境づくりにつながります。
あなたも自分に合った支援を見つけることで、生活の質を向上させることができるかもしれません。
発達障害の相談窓口と利用できる支援サービス
発達障害かなと思ったとき、どこに相談すればよいのでしょうか。いくつかの相談窓口と支援サービスをご紹介します。
相談窓口
発達障害の相談ができる主な窓口は以下の通りです。
- 発達障害者支援センター:各都道府県に設置されており、発達障害に関する相談や支援を行っています
- 精神保健福祉センター:こころの健康に関する相談ができます
- 保健センター:地域の保健師に相談できます
- 医療機関:精神科、心療内科、発達障害専門外来などで診断や治療を受けられます
当院のような発達障害の診断・治療を行っている医療機関では、発達障害スクリーニング検査により、自閉症(ASD)、アスペルガー障害、ADHDの診断も可能です。
利用できる支援サービス
発達障害と診断された場合、以下のような支援サービスを利用できる可能性があります。
- 障害者手帳:精神障害者保健福祉手帳を取得できる場合があります
- 就労支援:障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、ハローワークの専門窓口などで就労支援を受けられます
- 福祉サービス:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などのサービスがあります
- 教育支援:大学などの教育機関では、合理的配慮の提供を受けられる場合があります
これらのサービスを利用するには、医師の診断書や障害者手帳が必要な場合があります。詳細は各窓口にお問い合わせください。
発達障害の特性は人それぞれ異なります。自分に合った支援を見つけることで、より充実した生活を送ることができるでしょう。
まとめ:大人の発達障害と向き合うために
大人の発達障害は、生まれつきの脳の働き方の違いによるものであり、本人の努力不足や育て方が原因ではありません。社会に出てから初めて気づくケースも多く、適切な理解と支援が重要です。
自閉スペクトラム症(ASD)は社会的コミュニケーションの困難さとこだわりの強さ、注意欠如・多動症(ADHD)は不注意、多動性、衝動性が特徴です。限局性学習障害(LD)や感覚過敏も発達障害と関連する重要な特性です。
発達障害の診断は、精神科や心療内科など専門医療機関で行われます。診断を受けることで自己理解が深まり、適切な対処法や支援サービスを利用できるようになります。
治療・支援には、薬物療法、精神療法、環境調整など多角的なアプローチがあります。発達障害者支援センターや精神保健福祉センターなどの相談窓口も利用できます。
発達障害の特性は、環境との相互作用によって欠点にも長所にもなり得ます。自分の特性を理解し、適切な支援を受けることで、その人らしい充実した生活を送ることができるでしょう。
生きづらさを感じている方は、ぜひ専門家に相談してみてください。当院シモキタよあけ心療内科では、発達障害の診断・治療を行っています。一人ひとりの特性に合わせた支援を提供し、より良い生活の実現をサポートいたします。
詳しい情報や受診をご希望の方は、シモキタよあけ心療内科のウェブサイトをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。あなたの一歩を応援しています。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医