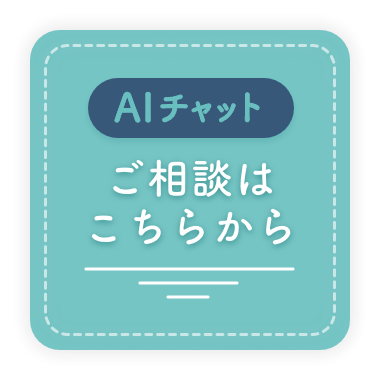2025年10月15日

ADHDと傷病手当金の関係性|受給は可能なのか
ADHDの方が傷病手当金を受給できるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、ADHDそのものを直接の理由として傷病手当金を受給するのは難しいケースが多いです。
ADHDは生まれつきの特性であり、「業務外で新たに発症した病気やケガ」という傷病手当金の基本的な受給条件に合致しにくいためです。
しかし、ADHDの方が職場環境に適応できずに二次的にうつ病や適応障害を発症した場合は、その二次的な疾患を理由として傷病手当金を申請できる可能性があります。
私の臨床経験からも、ADHDの特性がある方が職場で困難を抱え、そこから二次的な精神疾患を発症するケースは少なくありません。このような場合、適切な診断と治療が重要になります。
傷病手当金とは|基本的な仕組みと目的
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給される給付金です。健康保険に加入している被保険者(会社員やパート・アルバイトなど)が対象となります。
この制度の目的は、病気やケガで働けなくなった方とその家族の生活を経済的に支えることにあります。収入が途絶えることによる不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えるための重要なセーフティネットと言えるでしょう。

傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6か月を上限として受給できます。2022年1月からは支給期間の通算化が実施され、一度職場復帰した後に再び同じ病気で休職した場合でも、残りの期間分の給付を受けられるようになりました。
これはうつ病などの再発しやすい疾患を抱える方にとって、大きなメリットとなる制度改正です。
傷病手当金の受給条件|ADHDの場合の注意点
傷病手当金を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 健康保険に加入している(国民健康保険は原則対象外)
- 業務外の事由による病気やケガで療養している
- 仕事に就くことができない状態である
- 連続する3日間を含め4日以上仕事を休んでいる
- 休業期間中に給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)
ADHDの方が傷病手当金を申請する際の最大の注意点は、ADHDそのものは生まれつきの特性であるため、「業務外で新たに発症した病気」という条件に合致しにくい点です。
しかし、ADHDの特性により職場環境に適応できず、二次的にうつ病や適応障害などを発症した場合は、その二次的な疾患を理由として傷病手当金を申請できる可能性があります。
このような場合、医師の診断と「労務不能」の証明が重要になります。単に「ADHDがある」というだけでは不十分で、「うつ状態により労務遂行が困難」といった診断が必要です。
傷病手当金の申請には医師の診断書が必須となりますので、症状について詳しく医師に相談することをお勧めします。
ADHDに関連した傷病手当金申請の実際
ADHDの方が傷病手当金を申請するケースでは、一般的に「職場での不適応によって心身の状態を崩し、うつ病や適応障害となった」というパターンが多いです。
うつ病や適応障害になると、思うように体が動かず、働くことが困難になります。この状態が「労務不能」と判断され、傷病手当金の支給対象となるのです。

傷病手当金の申請では、必ず事前に医療機関を受診し、診断を受ける必要があります。うつ状態などの症状が重い場合、医療機関への受診自体が大きな負担となることもありますが、経済的支援を受けるためには必須のステップです。
私の診療経験からも、ADHDの特性がある方が職場環境との不適合から二次的な精神疾患を発症するケースは少なくありません。このような場合、適切な診断と休養、そして経済的支援が回復への重要な要素となります。
傷病手当金は給与の約3分の2が支給されるため、治療に専念するための大きな助けとなります。
傷病手当金の支給額と期間|ADHDと二次障害の場合
傷病手当金の支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額を30日で割り、その3分の2が1日あたりの支給額となります。簡単に言えば「給与の約3分の2」と考えておくとよいでしょう。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月が上限です。2022年1月からは支給期間の通算化が実施され、一度職場復帰した後に再び同じ病気で休職した場合でも、残りの期間分の給付を受けられるようになりました。
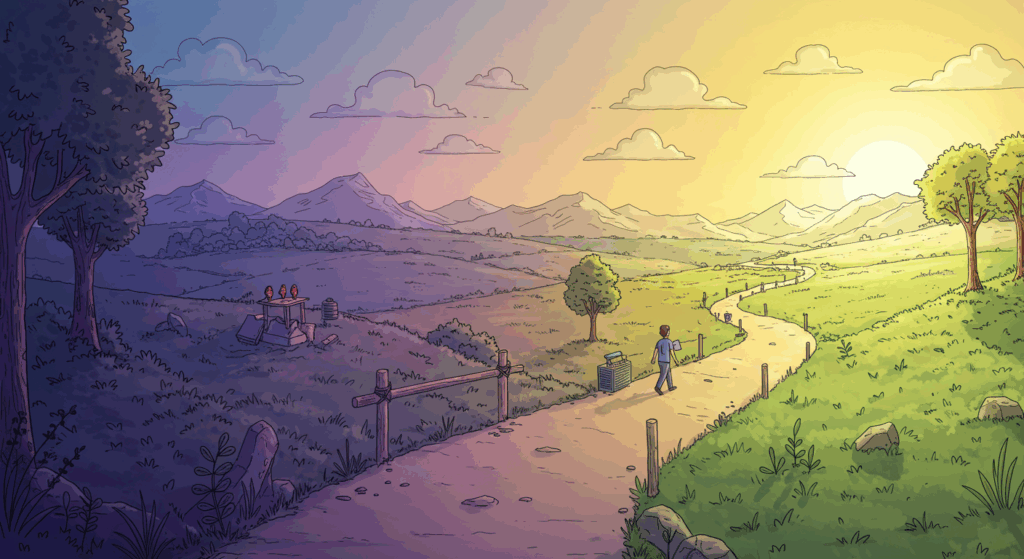
特にADHDの方が二次的に発症したうつ病や適応障害は、症状の波があったり、一度改善しても再発したりすることがあります。支給期間の通算化により、こうした症状の波に対応しやすくなったと言えるでしょう。
ただし、傷病手当金は高額な給付であるため、他の給付金との併給調整があります。例えば、同じ傷病で障害厚生年金を受給している場合、傷病手当金は調整されます。
ADHDの方が二次的な精神疾患で休職する場合、回復までの期間は個人差が大きいため、医師と相談しながら治療計画を立てることが重要です。
傷病手当金と障害年金の関係|ADHDの場合の選択肢
傷病手当金の支給期間(最大1年6ヶ月)を超えて療養が必要な場合、次の経済的支援として障害年金の検討が必要になることがあります。
ADHDそのものは先天的な特性ですが、それによる社会生活上の困難が著しい場合は障害年金の対象となる可能性があります。また、ADHDに起因する二次的な精神疾患(うつ病など)が重症化・長期化した場合も、障害年金の申請を検討する価値があります。
傷病手当金と障害年金には併給調整があり、同一の傷病で両方を受給する場合は調整が行われます。一般的には、障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額より多い場合、傷病手当金は支給されません。
ADHDの方が長期的な支援を必要とする場合、傷病手当金から障害年金へのスムーズな移行を考慮した計画が重要です。初診日や障害認定日など、障害年金申請に必要な要件を満たすためには、医療機関との継続的な関わりが欠かせません。
傷病手当金と障害年金は制度の目的や支給条件が異なるため、自分の状況に合わせて適切な制度を選択することが大切です。必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談することも検討してください。
ADHDと休職からの復職支援|傷病手当金受給後の選択肢
ADHDの方が二次的な精神疾患で休職し、傷病手当金を受給した後の復職については、慎重な計画が必要です。回復の度合いや職場環境によって、選択肢は異なります。
復職が可能な場合は、段階的な復職(リハビリ出勤)や業務内容の調整など、職場との協力が重要になります。ADHDの特性に合わせた環境調整(業務の優先順位の明確化、静かな作業環境の確保など)を検討することで、再発予防につながります。
一方、元の職場への復帰が難しい場合は、傷病手当金の受給期間終了後に退職し、失業保険(雇用保険)を活用する選択肢もあります。
ADHDの方が失業保険を受給する場合、傷病手当金と失業保険を続けて受給することは可能ですが、同時に受給することはできません。重要なのは、失業したタイミングで失業保険の延長給付の手続きを行うことです。これを忘れると、失業保険の受給資格を失ってしまう可能性があります。
ADHDの特性がある方の中には、一般就労が難しい場合もあります。そのような場合は、就労移行支援や障害者雇用など、特性に合わせた働き方を検討することも選択肢の一つです。
いずれの選択肢においても、医療機関との継続的な関わりを持ちながら、自分の特性と状態に合った復職計画を立てることが重要です。
傷病手当金申請時の注意点|ADHDの方が押さえておくべきポイント
ADHDの特性がある方が傷病手当金を申請する際には、いくつかの重要なポイントがあります。特に、ADHDの特性として計画的な手続きや書類管理が苦手な場合があるため、以下の点に注意しましょう。
- 早めの医療機関受診と診断取得
- 申請書類の準備と提出期限の管理
- 継続的な医療機関への通院
- 症状の経過や治療状況の記録
- 職場との適切なコミュニケーション
傷病手当金の申請には、医師による「労務不能」の証明が必須です。ADHDそのものではなく、二次的に発症したうつ病や適応障害などの症状によって働けない状態であることを、医師に詳しく伝えることが重要です。
また、傷病手当金は過去2年間にわたって申請できますが、申請が遅れると支給のタイミングも遅れます。特にADHDの方は、期限管理が苦手な場合があるため、カレンダーへの記入やリマインダーの設定など、自分に合った方法で期限を管理することをお勧めします。
さらに、傷病手当金の申請手続きは複雑で、書類の記入や提出に困難を感じることもあるかもしれません。そのような場合は、家族や信頼できる人に協力を求めたり、職場の人事担当者に相談したりすることも検討してください。
まとめ|ADHDと傷病手当金の関係を理解して適切に活用しよう
ADHDそのものを直接の理由として傷病手当金を受給するのは難しいですが、ADHDの特性により職場環境に適応できず、二次的にうつ病や適応障害などを発症した場合は、その二次的な疾患を理由として傷病手当金を申請できる可能性があります。
傷病手当金を受給するためには、健康保険への加入、業務外の疾病、労務不能状態、連続3日以上の休業などの条件を満たす必要があります。また、医師による診断と証明が不可欠です。
傷病手当金の支給額は給与の約3分の2、支給期間は最大1年6ヶ月です。2022年1月からは支給期間の通算化が実施され、一度復職した後の再休職にも対応しやすくなりました。
長期的な療養が必要な場合は、傷病手当金から障害年金への移行も検討する価値があります。また、復職に向けては、職場環境の調整や段階的な復帰など、ADHDの特性に合わせた計画が重要です。
ADHDの特性がある方が経済的支援を受けながら適切に療養し、自分らしい働き方を見つけるためには、医療機関との継続的な関わりと、必要に応じた専門家(社会保険労務士など)への相談が役立ちます。
当院では、ADHDの診断・治療はもちろん、職場との関係調整や各種書類の作成など、患者さんの社会生活を総合的にサポートしています。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医