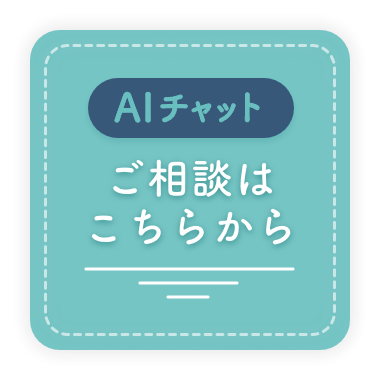2025年10月01日

傷病手当金とは?退職後も受給できる可能性がある制度
病気やケガで働けなくなったとき、収入が途絶えてしまうと生活に大きな影響を及ぼします。そんなときに頼りになるのが「傷病手当金」という制度です。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される手当です。精神疾患によって働けなくなった場合にも適用されます。
多くの方は「会社を辞めたら傷病手当金はもらえない」と思っているかもしれませんが、実は退職後でも一定の条件を満たせば受給できるのです。この記事では、傷病手当金の基本から退職後の受給条件まで、医師の立場から詳しく解説します。

私は精神科医として、うつ病や適応障害などで休職される患者さんと多く接してきました。その経験から言えることは、傷病手当金の制度を正しく理解していないために、受給できるはずの給付を受けられていない方が少なくないということです。
傷病手当金の基本的な受給条件
傷病手当金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは基本的な受給条件を確認しておきましょう。
傷病手当金を受け取るための条件は主に4つあります。
1. 業務外の病気やケガであること
傷病手当金は、仕事以外が原因の病気やケガで働けなくなった場合に支給されます。うつ病や適応障害などの精神疾患も対象です。
仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象となり、傷病手当金は支給されません。この区別は重要です。
2. 仕事ができない状態であること
医師が「労務不能」と診断することが必要です。つまり、これまで従事していた業務に就くことができない状態であると医師が認めることが条件となります。
単なる疲労や軽い風邪など、医師が労務不能と判断しない場合は支給対象になりません。
3.連続する3日間の待機期間があること
傷病手当金は、連続して3日間休んだ後(待機期間)、4日目以降の休業について支給されます。この3日間は、有給休暇を使用していても、土日祝日が含まれていても構いません。
ただし、待機期間の3日間は連続している必要があります。間に出勤日があると、待機期間はリセットされてしまいます。
4. 休業中に給与が支払われていないこと
休業期間中に会社から給与が支払われている場合は、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
例えば、傷病手当金の日額が8,000円で、会社から支払われる給与が日額5,000円の場合、差額の3,000円が支給されます。
傷病手当金の支給額と期間
傷病手当金がいくらもらえるのか、そしてどのくらいの期間もらえるのかは、多くの方が気になるポイントです。
精神科医として患者さんから最も多く質問を受ける内容の一つでもあります。ここでは具体的な金額と期間について説明します。
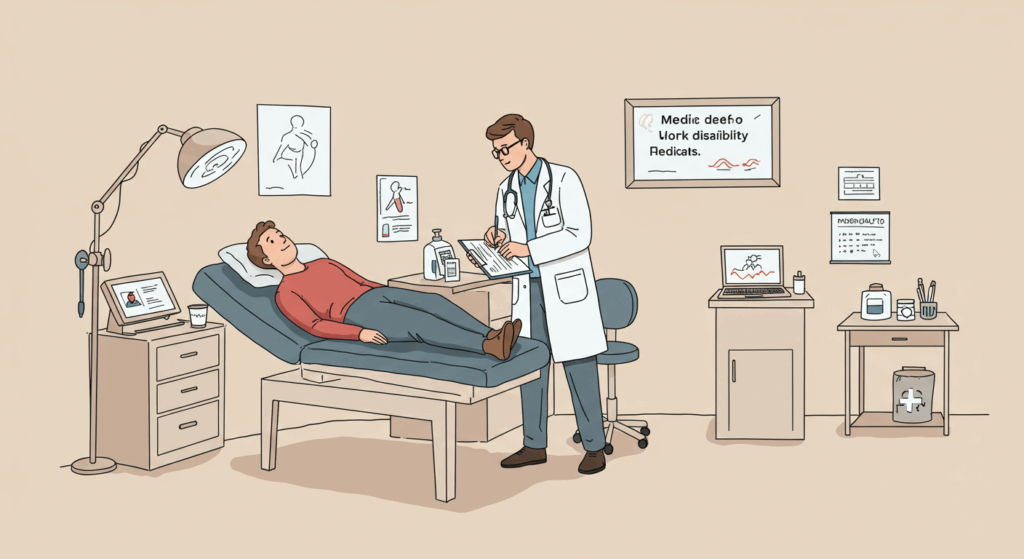
傷病手当金の支給額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、次の計算式で求められます。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額とは、健康保険料を計算するための基準となる金額で、給与や賞与などの報酬を元に決められています。
支給開始日の以前の期間が12カ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算されます。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(2025年3月31日以前の方は30万円、2025年4月1日以降の方は32万円)
傷病手当金の支給期間
傷病手当金は、支給開始日から最長1年6カ月間支給されます。2022年1月1日からは、「通算」1年6カ月となりました。
これは、一度職場復帰して再び同じ病気で働けなくなった場合でも、以前の支給期間と通算して1年6カ月まで受給できるということです。
例えば、6カ月間傷病手当金を受給した後に復職し、その後再び同じ病気で働けなくなった場合、残りの1年間は傷病手当金を受給できます。
退職後も傷病手当金を受給できる条件
ここからが本題です。退職後も傷病手当金を受給できる条件について詳しく見ていきましょう。
多くの方が知らないのですが、退職後でも一定の条件を満たせば、傷病手当金を受給することができます。
退職後の傷病手当金受給の5つの条件
退職後も傷病手当金を受給するためには、次の5つの条件をすべて満たす必要があります。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も休業していること
- 退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること
- 傷病手当金の支給開始日から休職日を通算して1年6ヵ月の範囲内であること
- 退職後働けない期間が継続していること
それぞれの条件について、詳しく解説していきます。
条件1: 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
健康保険(協会けんぽや健保組合)に継続して1年以上加入していることが必要です。この期間中に転職などで健康保険の種類が変わっても、加入が継続していれば問題ありません。
ただし、注意点があります。健康保険の任意継続被保険者である期間に発生した病気やケガについては支給されません。また、1年間のうち1日でも任意継続被保険者や国民健康保険に加入していた期間があると支給されません。
なお、退職後に任意継続被保険者や国民健康保険に加入しても、退職前から継続している傷病であれば傷病手当金は受給できます。
条件2: 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も休業していること
退職日の前日までに連続して3日間出勤しない「待期」が完成し、退職日も医師が働けないと認めて欠勤していることが条件です。
待期が完成していても、退職日に出勤してしまうと受給できなくなるので注意が必要です。これは見落としがちなポイントです。
条件3: 退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること
退職日と同一の病気やケガで働けない状態が続いていることが条件です。退職後に新たな病気で働けなくなった場合は、受給の対象とはなりません。
例えば、うつ病で休職中に退職した場合、退職後も同じうつ病で働けない状態が続いていることが必要です。
条件4: 傷病手当金の支給開始日から休職日を通算して1年6ヵ月の範囲内であること
受給できる期間は「支給開始日」から通算して1年6ヵ月の範囲内です。「退職日」から1年6ヵ月ではないことに注意が必要です。
例えば、すでに1年間傷病手当金を受給してから退職した場合、退職後は残りの6ヵ月間のみ受給できます。
条件5: 退職後働けない期間が継続していること
退職後は「在職期間からの継続給付」が条件となります。そのため、退職後に1日でも医師に「労務可能日(働ける状態)」と判断されれば、以降の傷病手当金は受給できません。
退職後に一度「仕事に就くことができる状態」になってアルバイトなどを行い、その後再び「仕事に就くことができない状態」になった場合、期間が残っていても再び手当を受け取ることはできません。
退職後に傷病手当金を申請する方法
退職後に傷病手当金を申請する方法について説明します。退職前と比べて若干手続きが異なる部分があるので、注意が必要です。
私の臨床経験から言うと、この手続きの複雑さに戸惑う患者さんは少なくありません。しっかり理解して、権利を失わないようにしましょう。
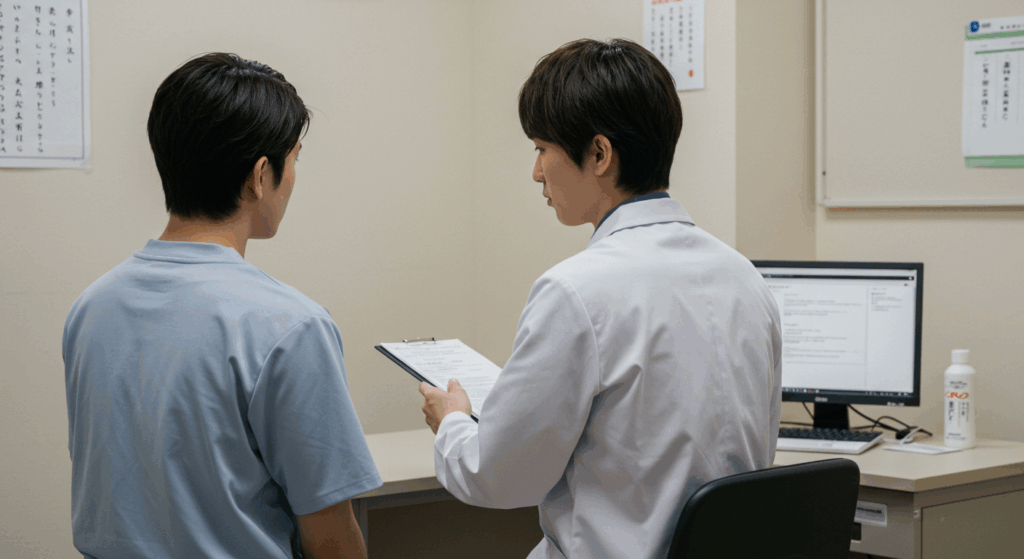
申請に必要な書類
傷病手当金の申請には、主に以下の書類が必要です。
- 傷病手当金支給申請書
- 医師の意見書(診断書)
- 退職証明書(退職後の申請の場合)
- その他、加入していた健康保険組合が指定する書類
退職後の申請では、勤務先の証明が得られない場合があります。その場合は、退職証明書や離職票などで代用できることがあります。
申請先と申請期限
申請先は、退職時に加入していた健康保険の保険者(全国健康保険協会や健康保険組合)です。
申請期限は、傷病手当金を受けることができる日の翌日から2年間です。期限を過ぎると時効となり、申請できなくなるので注意しましょう。
申請の流れ
退職後の傷病手当金申請の基本的な流れは以下の通りです。
- 医師の診察を受け、労務不能であることの証明を受ける
- 傷病手当金支給申請書を入手する(健康保険の窓口やウェブサイトから)
- 申請書に必要事項を記入する
- 医師に意見書部分の記入を依頼する
- 退職証明書などの必要書類を準備する
- 健康保険の窓口に申請書と必要書類を提出する
退職後は会社の協力が得られにくい場合もあります。その場合は、健康保険の窓口に相談してみましょう。
傷病手当金と他の給付との関係
傷病手当金は、他の給付と併給できない場合や調整が必要な場合があります。ここでは、主な関係について説明します。
特に退職後は、失業給付(失業保険)との関係が重要になってきます。
失業給付(失業保険)との関係
傷病手当金と失業給付は、同じ期間に両方を受け取ることはできません。どちらか一方を選ぶ必要があります。
一般的に、傷病手当金の方が失業給付よりも支給額が高い場合が多いですが、個人の状況によって異なります。また、傷病手当金の受給期間は失業給付の受給期間に算入されないため、傷病手当金を受給した後に失業給付を受けることも可能です。
うつ病などの精神疾患で休職している場合、「すぐに働ける状態」ではないため、失業給付よりも傷病手当金の方が適している場合が多いでしょう。
障害年金との関係
傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合、調整が行われます。障害年金の日額換算額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
例えば、傷病手当金の日額が8,000円で、障害年金の日額換算額が5,000円の場合、差額の3,000円が傷病手当金として支給されます。
老齢年金との関係
老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を受給している場合も、傷病手当金との調整が行われます。老齢年金の日額換算額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の高齢者の場合、この調整が関係してくることがあります。
よくある質問と注意点
最後に、傷病手当金に関するよくある質問と注意点をまとめます。
精神科医として患者さんから受ける質問の中から、特に重要なものをピックアップしました。
退職後に初めて傷病手当金を申請することはできますか?
在職中に傷病手当金の支給を受けていなくても、退職後に初めて申請することは可能です。ただし、先に説明した5つの条件をすべて満たしている必要があります。
特に重要なのは、退職日の前日までに連続して3日以上休んでおり、退職日も休んでいることです。これを満たしていないと、退職後の申請はできません。
傷病手当金はいつ振り込まれますか?
申請から支給までは、通常2週間から1カ月程度かかります。ただし、申請内容に不備がある場合や確認事項がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
経済的に困っている場合は、申請時にその旨を伝えると、優先的に処理してもらえる場合があります。
傷病手当金は課税対象ですか?
傷病手当金は非課税所得です。所得税や住民税の課税対象にはなりません。ただし、確定申告の際に申告する必要がある場合もありますので、詳しくは税務署や税理士にご相談ください。
注意点:医師の診断と証明が重要
傷病手当金の受給には、医師による「労務不能」の証明が不可欠です。特に退職後は、継続して働けない状態であることの証明が重要になります。
定期的に医師の診察を受け、労務不能の状態を適切に評価してもらうことが大切です。自己判断で通院をやめたり、診断書の取得を怠ったりすると、受給資格を失う可能性があります。
まとめ:傷病手当金は退職後も受給できる可能性がある
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときの経済的な支えとなる重要な制度です。そして、一定の条件を満たせば退職後も受給できることを覚えておきましょう。
退職後に傷病手当金を受給するための主な条件は以下の5つです。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も休業していること
- 退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること
- 傷病手当金の支給開始日から休職日を通算して1年6ヵ月の範囲内であること
- 退職後働けない期間が継続していること
特に注意すべきは、退職日も休業していることと、退職後も同じ病気で継続して働けない状態であることです。
傷病手当金の制度をしっかり理解し、必要なときに適切に申請することで、病気やケガの療養に専念できる環境を整えましょう。
メンタルヘルスの問題で休職されている方も、経済的な不安を軽減することで、回復に専念できる環境が整います。不明点があれば、主治医や健康保険の窓口に相談してみてください。
当院シモキタよあけ心療内科では、うつ病や適応障害などの精神疾患で休職されている方の診断書作成や傷病手当金の申請サポートも行っています。お困りの際はぜひご相談ください。
詳細はシモキタよあけの公式サイトをご覧ください。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医