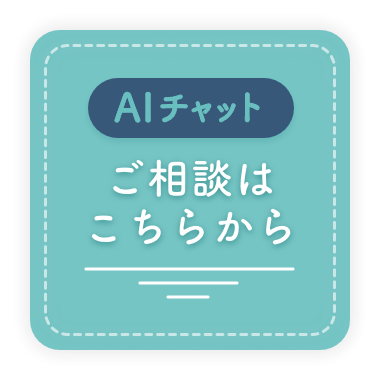2025年8月26日

睡眠障害と食欲不振の関係性
睡眠障害と食欲不振は、多くの精神疾患において同時に現れる重要な初期症状です。私が精神科医として日々の臨床で出会う患者さんの多くは、「眠れない」「食べられない」という訴えを持って来院されます。
これらの症状は、うつ病や不安障害をはじめとする様々な精神疾患の「赤信号」となることが少なくありません。特に注目すべきは、これらの症状が単独で現れるよりも、同時に出現することが多いという点です。
睡眠障害の中でも、寝つきはよいけれど夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」や、早朝3時や4時に目が覚めて二度と眠れなくなる「早朝覚醒」は、うつ病の特徴的な症状として知られています。これに食欲不振が伴うと、うつ病の可能性がより高まります。
私がこれまで診てきた患者さんの中には、「眠れないのはストレスのせいだと思っていた」「食欲がないのは単なる胃腸の調子の悪さだと思っていた」という方が非常に多いのです。しかし、これらの症状が2週間以上続く場合は、単なる一時的な不調ではなく、何らかの精神疾患のサインである可能性を考える必要があります。
睡眠障害の種類と見分け方
睡眠障害にはいくつかの種類があります。不眠症は、入眠障害(寝つきが悪い)、中途覚醒(眠りが浅く途中で何度も目が覚める)、早朝覚醒(早朝に目覚めて二度寝ができない)などの症状があり、そのために日中に倦怠感・意欲低下・集中力低下・食欲低下などの不調が出現する病気です。
一般成人の30〜40%が何らかの不眠症状を有しており、女性に多いことが知られています。不眠症状のある方のうち、慢性不眠症は成人の約10%に見られ、その原因はストレス、精神疾患、神経疾患、アルコール、薬剤の副作用など多岐にわたります。
特に注意が必要なのは、睡眠の質が低下している場合です。私の臨床経験から、単に睡眠時間が短いというだけでなく、睡眠の質が悪いと訴える患者さんは精神疾患を抱えていることが多いと感じています。
例えば、東京都立松沢病院での研修時代に出会った30代の男性患者さんは、「眠っているはずなのに、全く休んだ感じがしない」と訴えていました。検査の結果、重度のうつ病と診断されましたが、本人は「自分はうつ病ではない、ただ眠れないだけだ」と考えていたのです。
睡眠障害を見分けるポイントとして、以下の点に注目してください:
- 2週間以上にわたって睡眠の問題が続いているか
- 日中の活動に支障をきたしているか
- 睡眠薬を服用しても効果が限定的か
- 朝起きたときに疲労感が強く残っているか
- 睡眠に対する不安や過度の心配があるか
これらの症状が複数当てはまる場合は、単なる睡眠の問題ではなく、背景に精神疾患が隠れている可能性があります。早めに専門医への相談をお勧めします。
食欲不振が示す心の危険信号
食欲不振は、多くの精神疾患において見られる重要な症状です。特にうつ病では、食欲低下が特徴的な症状の一つとして知られています。
私が診療している患者さんの中には、「食べ物の味がしない」「食べる意欲が湧かない」「食べても美味しく感じない」と訴える方が少なくありません。これらは単なる好みの問題ではなく、脳内の報酬系や快感を感じる機能が低下している可能性を示唆しています。
食欲不振が危険信号となるのは、それが単に「食べたくない」という感覚を超えて、体重減少や栄養失調などの身体的問題につながる可能性があるからです。また、食欲不振は社会的な活動の減少にもつながります。食事は社交の重要な要素であり、食べることへの興味の喪失は、人間関係の希薄化や社会的孤立を招くことがあります。
食欲不振を見分けるポイントとしては、以下の点に注目してください:
- 2週間以上にわたって食欲の低下が続いているか
- 明らかな体重減少が見られるか(1ヶ月で5%以上の減少など)
- 食べることへの興味や楽しみが失われているか
- 食事の量が明らかに減少しているか
- 「食べなければならない」という義務感だけで食べているか
これらの症状が見られる場合は、背景に精神的な問題が隠れている可能性があります。特に睡眠障害と併せて現れる場合は、専門医への相談を強くお勧めします。
うつ病と睡眠障害・食欲不振の関連性
うつ病の初期症状として、睡眠障害と食欲不振は非常に重要です。厚生労働省の発表によると、うつ病は人口の3%、約365万人が罹患している病気で、女性が一生のうちにかかる確率は15~20%とされています。決して珍しい病気ではないのです。
うつ病における睡眠障害の特徴は、寝つきはよいけれど夜中に何度も目が覚めてしまう熟眠障害や、早朝に目が覚めて眠れなくなるパターンが多く見られることです。また食欲不振については、単に食べたくないというだけでなく、「食べ物の味がしない」「何を食べても美味しくない」という症状が特徴的です。
私が東京都立松沢病院で研修していた頃、40代の女性患者さんが印象に残っています。彼女は当初、単なる不眠症として他院で睡眠薬を処方されていましたが、症状が改善せず当院を受診しました。詳しく話を聞くと、不眠だけでなく食欲も低下しており、3ヶ月で5kgの体重減少があったことがわかりました。
さらに、「何をしても楽しくない」「朝起きるのがつらい」といった気分の落ち込みも認められ、うつ病と診断。適切な抗うつ薬治療を開始したところ、2ヶ月ほどで睡眠障害と食欲不振の両方が改善し、その後社会復帰を果たしました。
このケースからもわかるように、睡眠障害と食欲不振が同時に現れる場合は、うつ病を疑う重要なサインとなります。特に以下のような症状が加わる場合は、うつ病の可能性が高くなります:
- 興味や喜びの喪失(以前は楽しめていたことが楽しめなくなる)
- 疲労感や気力の低下
- 自己評価や自信の低下
- 不適切な罪責感や無価値感
- 思考力や集中力の低下
- 自殺念慮
うつ病は早期発見・早期治療が非常に重要です。睡眠障害と食欲不振が2週間以上続く場合は、精神科や心療内科への受診をお勧めします。
季節性感情障害と身体症状
季節性感情障害(SAD)は、秋から冬にかけてうつ症状が現れ、春先の3月ごろになるとよくなるというパターンを繰り返す精神疾患です。1984年に精神科医のローゼンタールらにより「冬季うつ病」として初めて報告されました。
この障害の特徴は、季節性があるという点です。診断するためには、明らかな心理的原因となる出来事やライフイベントが原因となっていないことが必要です。
有病率は、欧米では1~10%とされていて、日本の一般人口を対象に行なった調査においては、2.1%にSADが疑われたと報告されています。発症年齢は20歳代前半で、女性に多く、冬季に反復する場合の有病率は緯度、年齢、性別により差があり、高緯度地方では増大するといわれます。
私が診療している患者さんの中にも、毎年10月から11月頃になると決まって調子を崩す方がいます。典型的な症状としては、睡眠時間の増加、食欲増進(特に炭水化物への渇望)、体重増加などが挙げられます。
これは通常のうつ病とは異なる点で、一般的なうつ病では睡眠障害(不眠)と食欲不振が特徴的ですが、SADでは過眠と過食が見られることが多いのです。しかし、中には通常のうつ病と同様に、不眠や食欲低下を示す方もいます。
季節性感情障害の身体症状としては、以下のようなものが挙げられます:
- 過眠(通常より2時間以上長く眠る)
- 過食(特に炭水化物への渇望)
- 体重増加
- 極度の疲労感
- 活動量の低下
SADの治療としては、光療法(明るい光を浴びる治療法)が効果的とされています。また、抗うつ薬による薬物療法や認知行動療法なども有効です。
季節の変わり目に毎年同じような症状が現れる場合は、SADの可能性を考慮し、専門医に相談することをお勧めします。
自律神経失調症と睡眠・食欲の問題
自律神経失調症は、自律神経系のバランスが崩れることで様々な身体症状が現れる状態です。自律神経は、心拍数、血圧、呼吸、体温、消化活動など、私たちの体の基本的な機能を無意識のうちにコントロールしています。
この自律神経のバランスが崩れると、様々な身体症状が現れますが、その中でも特に多いのが睡眠障害と食欲の変化です。
自律神経失調症における睡眠障害は、入眠障害(寝つきの悪さ)や中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)として現れることが多いです。また、食欲については、増加する場合と減少する場合の両方があり、個人差が大きいのが特徴です。
私がシモキタよあけ心療内科で診ている患者さんの中には、「朝起きても疲れが取れない」「食事の時間になっても空腹を感じない」と訴える方が多くいらっしゃいます。これらの症状は、自律神経失調症の典型的な症状と言えます。
自律神経失調症の症状としては、以下のようなものが挙げられます:
- 睡眠障害(寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める)
- 食欲の変化(増加または減少)
- 疲労感・倦怠感
- めまい・立ちくらみ
- 動悸・息切れ
- 頭痛
- 胃腸の不調(腹痛、下痢、便秘など)
- 発汗異常(多汗または発汗減少)
自律神経失調症は、現代社会のストレスフルな環境の中で増加傾向にあります。特に、長時間労働やデジタルデバイスの過剰使用、不規則な生活リズムなどが原因となることが多いです。
治療としては、生活習慣の改善(規則正しい睡眠・食事、適度な運動など)が基本となります。また、必要に応じて自律神経を整える薬物療法や、リラクゼーション技法の習得なども効果的です。
睡眠障害と食欲の変化が長期間続く場合は、自律神経失調症の可能性も考慮し、専門医に相談することをお勧めします。
早期発見のためのセルフチェックポイント
睡眠障害と食欲不振は、様々な精神疾患の初期症状として現れることが多いため、早期発見が非常に重要です。以下に、自分自身や家族の状態をチェックするためのポイントをまとめました。
【睡眠に関するチェックポイント】
- 寝つきに30分以上かかることが週に3日以上ある
- 夜中に2回以上目が覚めることが週に3日以上ある
- 早朝(3〜4時頃)に目が覚めて、その後眠れないことが週に3日以上ある
- 十分な時間寝ているのに、日中の眠気や疲労感が強い
- 睡眠薬を服用しても効果が十分でない
- 睡眠について過度に心配したり、不安を感じたりする
【食欲に関するチェックポイント】
- 2週間以上にわたって食欲が明らかに低下している
- 1ヶ月で5%以上の体重減少がある(例:60kgの人なら3kg以上)
- 食べ物の味がしない、または美味しく感じない
- 食事をするのが義務のように感じる
- 食事の量が明らかに減少している
- 食事に対する興味や楽しみが失われている
【その他の精神症状のチェックポイント】
- 気分が落ち込み、何をしても楽しめない
- 以前は興味があったことへの関心が失われている
- 疲れやすく、気力が低下している
- 自分には価値がないと感じる、または過度に自分を責める
- 集中力や決断力が低下している
- 死について考えることが増えた
これらのチェックポイントのうち、複数の項目に当てはまる場合は、何らかの精神疾患の可能性があります。特に、睡眠障害と食欲不振の両方が見られる場合は、うつ病などの気分障害を疑う重要なサインとなります。
私の臨床経験から言えば、これらの症状に早めに気づき、適切な治療を受けることで、多くの方が回復への道を歩むことができています。症状に気づいたら、一人で抱え込まず、精神科や心療内科などの専門医に相談することをお勧めします。
専門医への相談のタイミングと方法
睡眠障害や食欲不振などの症状がある場合、どのタイミングで専門医に相談すべきか、また、どのように相談すればよいのかについて解説します。
まず、専門医への相談を検討すべきタイミングとしては、以下のような場合が挙げられます:
- 睡眠障害や食欲不振が2週間以上続いている
- これらの症状によって日常生活や仕事、学業に支障が出ている
- 市販の睡眠薬や生活習慣の改善を試みても効果がない
- 気分の落ち込みや不安感など、他の精神症状も伴っている
- 自殺について考えることがある(この場合は緊急で受診してください)
次に、専門医への相談方法についてですが、精神科や心療内科を受診する際には、以下のような準備をしておくとスムーズです:
- 症状のメモを作成する(いつから、どのような症状が、どのくらいの頻度や強さで現れているか)
- 現在服用している薬があれば、その情報(お薬手帳など)を持参する
- 過去の病歴や家族の精神疾患の有無についての情報を整理しておく
- 日常生活や仕事、人間関係などで気になることがあれば、それもメモしておく
初診時には、医師からさまざまな質問をされます。「眠れていますか?」「食欲はありますか?」といった質問は、単なる世間話ではなく、診断のための重要な情報収集です。正確な診断と適切な治療のために、できるだけ正直に答えることが大切です。
私がシモキタよあけ心療内科で初診の患者さんを診る際には、まず症状の経過や生活背景を丁寧に聞き取ります。そして、必要に応じて心理検査や血液検査などを行い、総合的に診断を進めていきます。
精神科や心療内科を受診することに抵抗を感じる方も多いかもしれませんが、現在では精神疾患は特別なものではなく、風邪や腰痛と同じように誰でもかかりうる病気として認識されています。早期に適切な治療を受けることで、多くの精神疾患は改善・回復が可能です。
もし受診に不安を感じるなら、信頼できる家族や友人に付き添ってもらうのも良いでしょう。また、初めから精神科を受診するのに抵抗がある場合は、まずかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらう方法もあります。
大切なのは、症状に気づいたら一人で抱え込まず、専門家に相談することです。適切な治療によって、多くの方が症状の改善を実感し、健康な日常生活を取り戻しています。
まとめ:心と体のサインを見逃さないために
本記事では、睡眠障害と食欲不振という、一見すると単なる体調不良と思われがちな症状が、実は様々な精神疾患の重要なサインとなることを解説してきました。
これらの症状は、うつ病、不安障害、季節性感情障害、自律神経失調症など、多くの精神疾患において初期症状として現れることが多く、早期発見・早期治療のための重要な手がかりとなります。
特に重要なポイントをまとめると:
- 睡眠障害(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒)と食欲不振が2週間以上続く場合は、精神疾患のサインである可能性があります
- これらの症状が同時に現れる場合は、うつ病などの気分障害を疑う重要な手がかりとなります
- 季節性感情障害では、秋から冬にかけて症状が悪化し、春になると改善するという季節性のパターンが特徴です
- 自律神経失調症では、睡眠障害に加えて、食欲の変化(増加または減少)が見られることがあります
- 早期発見のためには、自分自身や家族の状態を定期的にチェックすることが大切です
- 症状に気づいたら、一人で抱え込まず、専門医に相談することをお勧めします
精神疾患は、適切な治療を受けることで多くの場合改善・回復が可能です。しかし、症状を放置すると慢性化したり、重症化したりするリスクがあります。
私たち精神科医が日々の診療で実感しているのは、早期発見・早期治療の重要性です。「ただの不調だろう」「もう少し様子を見よう」と思って放置してしまうケースが少なくありません。しかし、心と体のサインに早めに気づき、適切な対応をすることで、回復への道のりはずっと短くなります。
心配な症状がある場合は、ぜひ専門医に相談してください。シモキタよあけ心療内科では、睡眠障害や食欲不振をはじめとする様々な症状に対して、専門的な診断と治療を提供しています。一人ひとりの状態に合わせた丁寧な診療を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
心と体の健康は、充実した人生を送るための基盤です。小さなサインを見逃さず、早めの対応を心がけましょう。
詳しい情報や受診方法については、シモキタよあけ心療内科のウェブサイトをご覧ください。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医