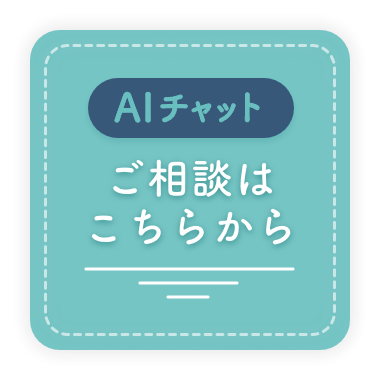2025年11月25日

不眠症とストレスの密接な関係
睡眠の悩みを持つ人は3人に1人、不眠症は10人に1人と言われています。日々の生活の中で「なかなか眠れない」「夜中に何度も目が覚める」といった経験をされた方も多いのではないでしょうか。
不眠症とストレスには密接な関係があります。ストレスが原因で眠れない期間が長く続くと、不眠症に移行してしまう可能性があるのです。
強いストレスを感じると交感神経が優位に働き、脳や体が緊張状態になります。夜になっても副交感神経に切り替わらず、リラックスできなくなってしまうのです。
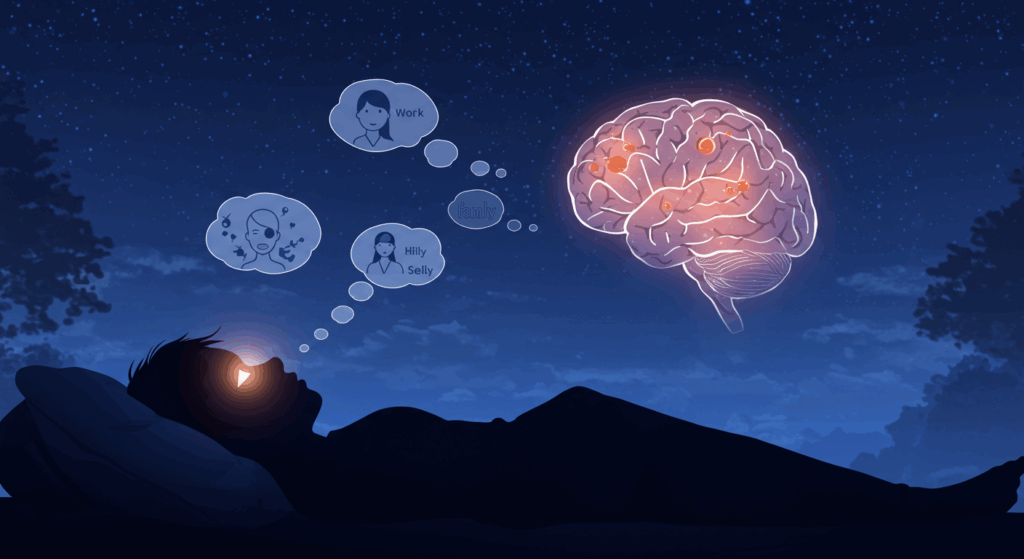
ストレス状態が続くと、自律神経のリズムが崩れ、眠れない日が続きます。一時的な睡眠困難が不眠症につながってしまうのです。
不眠症の診断基準は以下の通りです。
- 夜間の不眠が続く
- 日中に精神や体の不調を感じ生活の質が低下する
上記の症状が3カ月未満の場合は短期不眠症、それ以上続く場合は慢性不眠症と診断されます。慢性不眠症は日中の不調や不眠を感じるのが週3日以上あり、それが3カ月以上続いた場合です。
不眠症の4つのタイプとその特徴
不眠症には主に4つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解することで、自分がどのタイプに当てはまるのかを把握し、適切な対処法を見つける手がかりになります。
まずは自分の不眠がどのタイプなのか確認してみましょう。
入眠障害(寝付きが悪い)

布団に入ってもなかなか眠れず、眠りにつくまでに30分〜1時間以上かかる状態です。特に、不安やストレス、緊張感が高いときに起こりやすく、「今夜も眠れないかもしれない」という不安そのものが、さらに眠れなくするという悪循環に陥ることもあります。
若年層や、神経が過敏な人に多くみられるタイプです。
中途覚醒(途中で何度も目が覚める)
夜中に何度も目が覚めてしまい、その後再び寝つけない状態です。特に中高年以降になると、加齢に伴い眠りが浅くなるため、中途覚醒が起こりやすくなります。
夜間にトイレに行く回数が増える、周囲の音や明るさに敏感になるなども一因です。日本人の成人における不眠症状の中で最も多く見られるタイプとされています。
早朝覚醒(朝早く目が覚めてしまう)
自分が望む時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れないという状態です。高齢者に多く、また、うつ病の代表的な症状のひとつでもあります。
朝の気分の落ち込みや意欲の低下を伴う場合は、早期に専門医への相談が勧められます。
熟眠障害(ぐっすり眠れた気がしない)
睡眠時間は足りているはずなのに、「眠った気がしない」「疲れが取れない」と感じる状態です。睡眠の質が浅いため、起きたときにスッキリ感が得られません。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)や、周期性四肢運動障害(PLMD)など、睡眠中に身体の異常が現れる疾患が原因となっているケースもあります。
これらの不眠症状は、1つだけ現れる場合もあれば、複数が同時に現れるケースもあります。特に高齢者では、入眠障害と中途覚醒が同時に起こるなど、複合的な不眠症状を訴える人が多い傾向にあります。
不眠のタイプによって、適した対処法や治療法は異なるため、まずは自分の不眠がどのタイプに当てはまるのかを把握することが、改善への第一歩となります。
不眠につながるストレスの主な原因

厚生労働省の「令和4年度 健康実態調査結果の報告」によると、悩みやストレスの原因として上位に挙げられているのは、自分や家族の健康状態、収入・家計・借金、仕事、人間関係などです。
これらのストレスは不眠へとつながる可能性が高いと考えられます。
健康上の悩み
健康の悩みがストレスになり、不眠を引き起こすことがあります。年齢を重ねると病気になる可能性が高まり、不安を抱えやすくなるためです。
厚生労働省の国民基礎調査を見ると、35歳以降で何らかの体調不良を訴える方が増加傾向にあります。40代以降では、更年期障害により心身の調子を崩すことも考えられます。
体調不良は心身に大きなストレスを与えますし、将来への不安から眠れなくなる可能性もあるでしょう。
仕事のストレス
働く人の中で強いストレスを感じている割合は、約58%と言われています。約60%の働く人は、仕事の質と量が原因であると感じています。
一方、対人関係、仕事で失敗することについて、約30%の人が、ストレスの要因として感じています。
仕事上の人間関係から来るストレスが、あなたの睡眠を妨げ、知らないうちに、体とこころの不調をきたしているかもしれません。
家庭問題
家族に関する問題がストレスになり、不眠を引き起こす可能性があります。解決に時間がかかることも多く、ストレスを感じやすいためです。
子育て中、子どもの反抗期や進路問題などでストレスを抱えるケースが考えられます。母親の更年期と重なり、余計にストレスを感じるかもしれません。
年齢を重ねると親の介護問題もストレスの原因となります。介護のストレスは、誰が面倒をみるのか、相続はどうなるかなど、次世代も関係することもあります。
経済的な問題
収入・家計・借金などの経済的な問題もストレスの大きな原因です。生活の基盤に関わる問題だけに、不安が大きくなりやすく、夜になると考え込んでしまうことも少なくありません。
特に現在の経済状況では、将来への不安から経済的なストレスを感じる人が増えています。
ストレスによる不眠症状の特徴
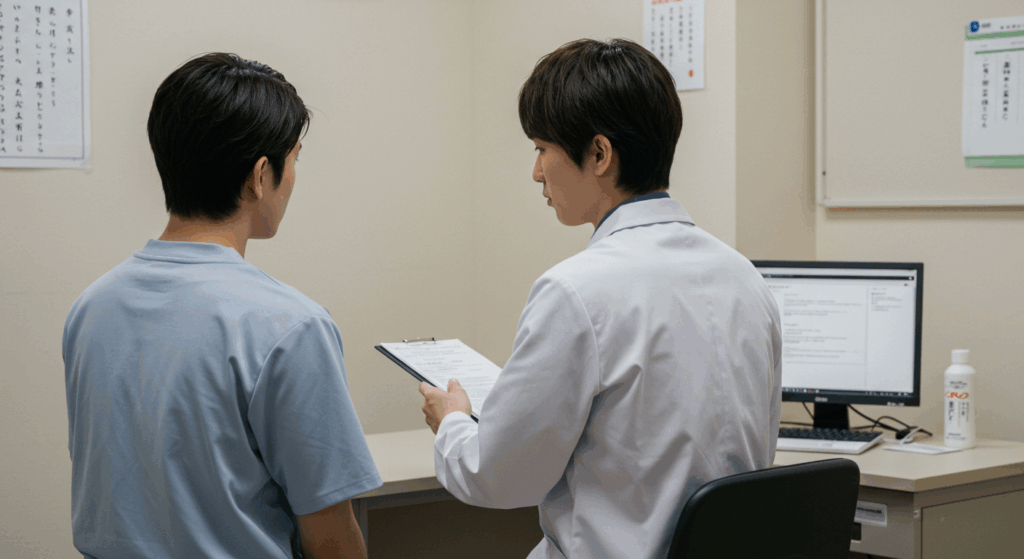
ストレスが原因で起こる不眠症には、いくつかの特徴的な症状があります。自分の症状がこれらに当てはまるかどうか確認してみましょう。
入眠困難(ベッドに入ってもすぐに眠れない)
ストレスを感じると、脳が活発に働き、考えごとが止まらなくなります。布団に入っても、仕事のこと、家族のこと、健康のことなど、さまざまな心配事が頭をめぐり、なかなか眠りにつけません。
「早く眠らなければ」という焦りがさらに睡眠を遠ざけてしまうこともあります。
中途覚醒(途中で何度も目が覚める)
いったん眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまいます。ストレスによって自律神経のバランスが崩れ、少しの物音や光でも敏感に反応してしまうのです。
また、ストレスホルモンの一つであるコルチゾールの分泌が乱れることも、中途覚醒の原因となります。
早朝覚醒(朝早く目が覚める)
予定していた時間よりも早く目が覚めてしまい、その後眠れなくなります。特にうつ傾向がある場合に多く見られる症状です。
早朝に目が覚めると、その後また眠ろうとしても、不安や心配事が頭に浮かび、再び眠ることができなくなります。
熟眠感がない
十分な時間寝ているはずなのに、朝起きたときに「ぐっすり眠れた」という感覚がなく、疲れが取れていないと感じます。
ストレスによって睡眠の質が低下し、深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間が減少することが原因です。
重症になると、悪夢を見る人もいます。その場合は、寝ることに恐怖を感じるようになり、さらに不眠が悪化することもあります。
ストレスによる不眠のメカニズム
ストレスで不眠になるのは、脳が興奮状態になり自律神経のリズムが乱れるためと考えられています。自律神経は呼吸や体温、心臓の動きなどを調節する、生命維持に必要な体の機能をつかさどる神経です。
自律神経は交感神経と副交感神経にわかれています。交感神経は体を動かし、副交感神経はリラックスさせる働きを持ちます。
眠りにつくときは、自律神経の中で体をリラックスさせる作用のある副交感神経が優位になります。しかし、ストレスがあると、人が緊張するときに優位になる交感神経が活発になります。
そのため、眠れない症状が出現します。一旦、寝付いても眠りが浅い感じを受けます。
ストレスによって脳と体が警戒の状態に入ったような過度の覚醒が生じます。夜になると、寝つきが悪い、目が覚めても再び眠れない症状が出現します。
また、ストレスを感じると、コルチゾールやアドレナリンなどのストレスホルモンが分泌されます。これらのホルモンは体を活動的にする働きがあるため、夜になっても脳や体が興奮状態のままになってしまうのです。
さらに、ストレスを感じると、不安や心配事が頭から離れなくなります。布団に入ってリラックスしようとしても、ネガティブな思考が次々と浮かび、眠りを妨げてしまいます。
ストレスによる不眠症の7つの対処法
ストレスによる不眠症の対処法として、以下の7つの方法を紹介します。自分に合った方法を見つけて、ぜひ試してみてください。
1. 腹式呼吸で気持ちを落ち着かせる
腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。寝る前に5分程度、ゆっくりと腹式呼吸を行うことで、心身の緊張をほぐすことができます。
鼻から息を吸いながらお腹を膨らませ、口からゆっくりと息を吐きながらお腹をへこませます。この動作を繰り返すことで、自然と心が落ち着いてきます。
2. 体温と眠りの深い関係を活用する
入眠時には体温が下がることが重要です。寝る1〜2時間前に入浴し、体温を上げておくと、その後体温が下がる過程で眠気が促進されます。
38〜40℃のぬるめのお湯に20分程度つかり、体をじんわりと温めるのが効果的です。熱すぎるお湯は交感神経を刺激するので避けましょう。
3. 眠気を誘う食べ物や飲み物を活用する
トリプトファンを含む食品(バナナ、牛乳、豆腐など)は、セロトニンやメラトニンの生成を助け、睡眠の質を高める効果があります。
寝る前のホットミルクやハーブティー(カモミール、ラベンダーなど)も、リラックス効果があり、眠りを誘います。ただし、カフェインを含む飲み物は避けましょう。
4. 運動を習慣化する
適度な運動は、ストレス解消と良質な睡眠に効果的です。ただし、寝る直前の激しい運動は交感神経を刺激するため避け、寝る3時間前までに終えるようにしましょう。
ウォーキング、ストレッチ、ヨガなどの軽い運動が特におすすめです。
5. 寝る前のリラクゼーション
寝る前のリラックスタイムを設けることで、スムーズな入眠を促します。読書、音楽鑑賞、アロマテラピーなど、自分に合ったリラックス法を見つけましょう。
特に、スマートフォンやパソコンなどの電子機器は、ブルーライトの影響で眠りを妨げるため、寝る1時間前からは使用を控えることをおすすめします。
6. 筋弛緩法を試す
全身の筋肉を順番に緊張させてから弛緩させる筋弛緩法は、身体の緊張をほぐし、リラックス状態へと導きます。
足の指から始めて、ふくらはぎ、太もも、お腹、胸、腕、肩、首、顔へと順番に行っていきます。各部位を5〜10秒間緊張させた後、ゆっくりと力を抜きます。
7. 自律神経を整える三行日記
寝る前に、その日あった良かったことや感謝したことを3つ書き出す「三行日記」は、ポジティブな気持ちで眠りにつくのに役立ちます。
また、明日の予定や気になっていることを紙に書き出すことで、頭の中を整理し、余計な心配事を減らすことができます。
不眠症が続くときの専門的な対応

上記の対処法を試しても不眠症状が改善しない場合は、専門医への相談を検討しましょう。特に以下のような症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。
- 不眠が1カ月以上続いている
- 日中の眠気や集中力低下が著しい
- 不眠によって日常生活に支障が出ている
- 不眠に加えて、抑うつ感や不安感が強い
精神科や心療内科では、不眠症の原因を詳しく診断し、適切な治療法を提案してくれます。治療法としては、認知行動療法や必要に応じた薬物療法などがあります。
認知行動療法は、不眠症に対する非薬物療法として効果が認められています。睡眠に関する考え方や行動パターンを見直し、健康的な睡眠習慣を身につけることを目指します。
薬物療法では、症状や原因に応じて適切な睡眠薬が処方されることがあります。ただし、睡眠薬は医師の指示に従って正しく服用することが重要です。
不眠症は早期に適切な対応をすることで改善が期待できます。一人で悩まず、専門家に相談することで、より良い睡眠を取り戻しましょう。
まとめ:ストレスと不眠の関係を理解し、健やかな睡眠を
不眠症とストレスには密接な関係があります。ストレスによって自律神経のバランスが崩れ、眠りが妨げられることがわかりました。
不眠症には入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害の4つのタイプがあり、それぞれに適した対処法があります。まずは自分の不眠のタイプを知ることが大切です。
不眠につながるストレスの原因としては、健康上の悩み、仕事のストレス、家庭問題、経済的な問題などが挙げられます。これらのストレス要因を認識し、適切に対処することが重要です。
ストレスによる不眠症の対処法としては、腹式呼吸、入浴による体温調節、食事の工夫、適度な運動、リラクゼーション、筋弛緩法、三行日記などがあります。自分に合った方法を見つけて実践してみましょう。
それでも不眠症状が改善しない場合は、専門医への相談を検討してください。早期に適切な対応をすることで、より良い睡眠を取り戻すことができます。
質の良い睡眠は、心身の健康を維持するために欠かせません。ストレスと上手に付き合いながら、健やかな睡眠を手に入れましょう。
睡眠でお悩みの方は、下北沢駅から徒歩1分のシモキタよあけ心療内科にご相談ください。精神科専門医が丁寧に診察し、あなたに合った治療法をご提案いたします。シモキタよあけ心療内科では、不眠症をはじめとする様々な精神疾患に対応しています。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医