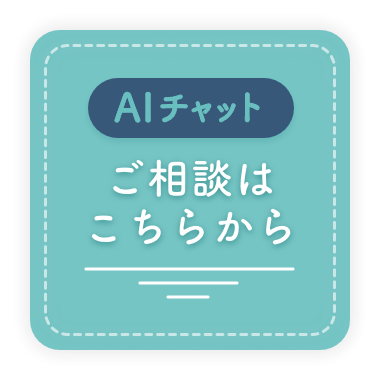2025年11月24日

不眠症に悩む方へ〜睡眠障害の基本理解
眠りたいのに眠れない。そんな悩みを抱える方は少なくありません。
不眠症は現代社会において非常に多くの方が抱える睡眠の問題です。日中の活動に支障をきたすほどの睡眠障害は、単なる一時的な睡眠不足とは異なり、心身の健康に大きな影響を与えます。精神科医として多くの患者さんの睡眠の悩みに向き合ってきた経験から、不眠症の本質と効果的な対処法についてお伝えしたいと思います。
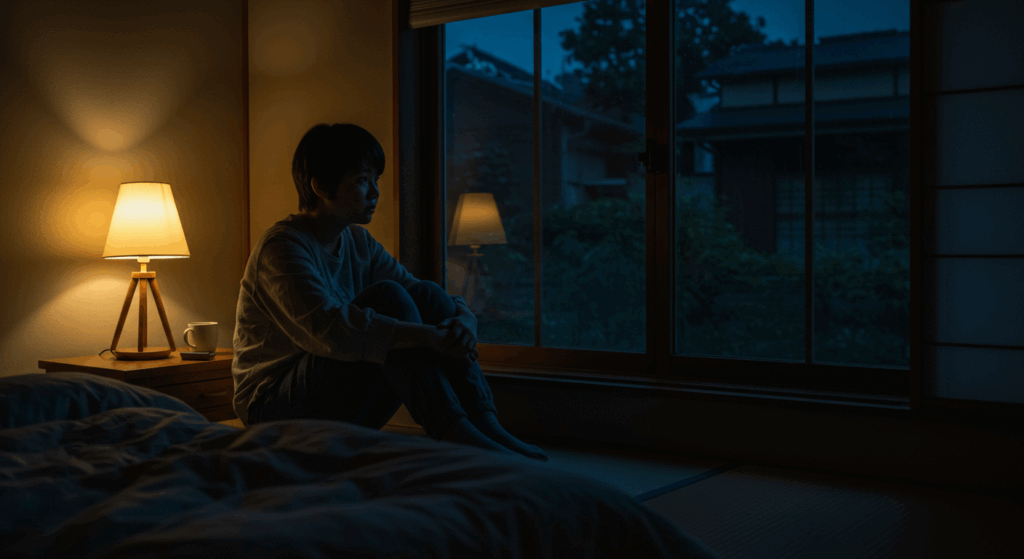
不眠症は単に「眠れない」という症状だけではなく、その現れ方にはいくつかのタイプがあります。自分がどのタイプに当てはまるのかを知ることで、より効果的な対処法を見つけることができるのです。
私たちの睡眠は、体内時計(概日リズム)、睡眠ホルモン(メラトニン)、そして睡眠圧(脳内に蓄積されるアデノシンによる眠気)という3つの要素によって調整されています。これらのバランスが崩れることで、様々な不眠の症状が現れるのです。
不眠症の4つのタイプとその特徴
不眠症には主に4つのタイプがあります。あなたはどのタイプに当てはまるでしょうか?
それぞれのタイプを理解することで、自分の睡眠の問題を客観的に捉えることができます。また、タイプによって効果的な対処法が異なるため、自分のタイプを知ることは改善への第一歩となります。
1. 入眠困難型(寝つきが悪い)
ベッドに入ってから30分以上経っても眠れない状態です。頭の中で考え事が巡り続けたり、身体がリラックスできなかったりすることが原因となります。
この入眠困難は、交感神経が活発に働いていることが多く、特に日中のストレスや不安が強い場合に起こりやすくなります。また、夜遅くまでスマホやパソコンを使用することで、ブルーライトの影響でメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなることもあります。
2. 中途覚醒型(夜中に何度も目が覚める)
一度は眠りにつくものの、夜中に何度も目が覚めてしまうタイプです。特に、再び眠りにつくことが難しい場合は、日常生活への影響が大きくなります。
中途覚醒の原因としては、ストレスや不安による自律神経の乱れ、身体的な問題(痛みや頻尿など)、環境要因(騒音や室温など)が考えられます。また、アルコールは入眠を促進する効果がありますが、代謝されると逆に覚醒作用をもたらすため、夜中に目が覚める原因となることがあります。

3. 早朝覚醒型(予定より早く目覚めてしまう)
朝早く(通常の起床時刻より2時間以上前)に目が覚めてしまい、その後眠ることができないタイプです。このタイプはうつ病との関連が強いことが知られています。
早朝覚醒は、体内時計の乱れや心理的ストレスが関係していることが多く、特に高齢者に多く見られます。また、睡眠時間が加齢とともに前倒しになる生理的な変化も影響しています。
4. 熟眠障害型(眠った気がしない)
十分な時間睡眠をとっているにもかかわらず、熟睡感が得られないタイプです。客観的には睡眠できていても、主観的な睡眠の質に問題があります。
熟眠障害は、睡眠の質が低下していることが原因で、特に深い睡眠(ノンレム睡眠)が減少していることが多いです。ストレスや不安、カフェインの過剰摂取、不規則な生活リズムなどが影響します。
不眠症タイプ別の効果的な対処法
それでは、各タイプの不眠症に対する効果的な対処法を見ていきましょう。
睡眠の問題は一人ひとり異なりますが、自分のタイプに合った対処法を実践することで、多くの場合改善が期待できます。ここでは、私が臨床現場で実際に患者さんに勧めている方法をご紹介します。
入眠困難型への対処法
入眠困難に悩む方には、就寝前のリラクゼーションが特に重要です。具体的には以下の方法が効果的です。
- 就寝1時間前からはスマホやパソコンの使用を控え、ブルーライトをカットする
- 入浴は就寝の1〜2時間前に済ませ、体温の自然な低下を促す
- 就寝前のルーティンを作り、脳に「もうすぐ眠る時間」という信号を送る
- 腹式呼吸や筋弛緩法などのリラクゼーション技法を実践する
- 寝室は睡眠のための場所と認識させ、ベッドで読書やスマホを見ることは避ける
特に効果的なのが「寝ようとし過ぎない」ことです。眠れないことに対する不安や焦りが、かえって覚醒を促進してしまいます。
もし15〜30分経っても眠れない場合は、一度ベッドから出て、dim lightの中でリラックスできる活動(読書など)をし、再び眠くなってからベッドに戻るのも良い方法です。

中途覚醒型への対処法
中途覚醒に悩む方には、睡眠環境の整備と夜間の覚醒要因の排除が重要です。
- 寝室の環境を整える(適切な室温、湿度、静かさ、暗さを確保)
- 夕方以降のカフェイン摂取を避ける(カフェインの半減期は約5〜6時間)
- 夕食は就寝の3時間前までに済ませ、消化不良を防ぐ
- 就寝前のアルコール摂取を控える(入眠は促進するが、睡眠後半の質を低下させる)
- 夜間の頻尿がある場合は、就寝前2時間の水分摂取を控える
目が覚めてしまった時に時計を見ることも避けましょう。「あと何時間しか眠れない」という焦りが、再入眠を困難にします。
早朝覚醒型への対処法
早朝覚醒に悩む方には、体内時計の調整が特に重要です。
- 毎日同じ時間に起床し、体内時計を安定させる
- 朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 朝食をしっかり摂り、体に「一日の始まり」という信号を送る
- 日中の適度な運動習慣をつける(ただし就寝の3時間前までに)
- うつ傾向がある場合は、専門医への相談も検討する
早朝覚醒は特にうつ病との関連が強いため、気分の落ち込みや意欲の低下などの症状がある場合は、睡眠の問題だけでなく、心の健康についても専門家に相談することをお勧めします。
熟眠障害型への対処法
熟眠障害に悩む方には、睡眠の質を高める工夫が重要です。
- 寝具の見直し(自分に合った枕や敷布団/マットレスを選ぶ)
- 日中の適度な身体活動で深い睡眠を促進する
- 就寝前のリラックスタイムを確保する
- 睡眠時無呼吸症候群などの身体的要因がないか専門医に相談する
- 睡眠の質を記録するアプリや機器を活用して客観的データを得る
熟眠障害は主観的な問題であることも多いため、実際の睡眠の質を客観的に評価することも有効です。
生活習慣から改善する不眠対策
不眠症の改善には、タイプ別の対処法に加えて、日常生活全体を見直すことも重要です。
睡眠は私たちの生活習慣全体と密接に関わっています。食事、運動、ストレス管理など、日中の過ごし方が夜の睡眠に大きく影響します。
規則正しい生活リズムの確立
良質な睡眠のためには、体内時計を整えることが基本となります。
- 休日も含めて毎日同じ時間に起床・就寝する
- 朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 食事の時間も規則的にする
- 昼寝をする場合は15〜30分程度にとどめ、午後3時以降は避ける
体内時計が整うと、適切なタイミングでメラトニンが分泌され、自然な眠気を感じやすくなります。

食事と栄養の見直し
食事内容も睡眠の質に影響します。特に以下の点に注意しましょう。
- トリプトファンを含む食品(乳製品、卵、大豆、バナナなど)を適度に摂る
- 夕食は就寝の3時間前までに済ませる
- カフェインの摂取は午後2時までにする
- 就寝前のアルコールは避ける(入眠は促進するが、睡眠の質を低下させる)
- 就寝前の喫煙も避ける(ニコチンには覚醒作用がある)
空腹で眠れない場合は、就寝1時間前に温かい牛乳やハーブティーなど、消化の良い軽い飲み物を摂るのも良いでしょう。
適度な運動習慣
適度な運動は深い睡眠を促進します。ただし、タイミングには注意が必要です。
- 有酸素運動を中心に、週3〜5回、30分程度の運動を習慣にする
- 運動は就寝の3時間前までに終えるようにする
- ストレッチや軽いヨガは就寝前のリラックスに効果的
激しい運動は体温を上昇させ、交感神経を活性化するため、就寝直前は避けましょう。
ストレス管理と心のケア
ストレスや不安は不眠の大きな原因となります。日常的なストレス管理が重要です。
- マインドフルネスや瞑想を取り入れる
- 趣味や楽しみの時間を確保する
- 悩みを信頼できる人に相談する
- 認知行動療法の技法を学ぶ(不眠に関する考え方のパターンを変える)
- 就寝前に「心配事ノート」をつけ、考え事を書き出して頭の中を整理する
特に就寝前の「考えすぎ」が入眠を妨げることが多いため、心を落ち着ける習慣を作りましょう。
専門的治療が必要なケース
セルフケアを試みても改善しない場合は、専門医への相談を検討しましょう。
不眠症は、他の身体疾患や精神疾患の症状として現れることもあります。また、長期間続く不眠は、生活の質を著しく低下させ、様々な健康リスクを高めます。
専門医を受診すべきタイミング
以下のような場合は、精神科や心療内科、睡眠専門クリニックの受診をお勧めします。
- 不眠が1ヶ月以上続いている
- 日中の眠気や疲労感が強く、日常生活に支障をきたしている
- いびきや呼吸停止、脚のむずむず感などの症状がある
- 不安や抑うつ感が強い
- 市販の睡眠薬を常用している
専門医は問診や検査を通じて、不眠の原因を詳しく評価し、適切な治療法を提案します。
不眠症の専門的治療法
医療機関での不眠症治療には、主に以下のようなアプローチがあります。
- 認知行動療法(CBT-I):不眠に特化した心理療法で、睡眠に関する考え方や行動パターンを改善する
- 薬物療法:症状や原因に応じて適切な睡眠薬を処方(ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など)
- 光療法:体内時計の調整を目的とした治療法
- 睡眠衛生指導:専門的な視点からの生活習慣改善アドバイス
- 基礎疾患の治療:睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、睡眠を妨げる疾患の治療
特に認知行動療法(CBT-I)は、薬に頼らない不眠治療として国際的に推奨されており、長期的な効果が期待できます。
まとめ:不眠症改善への第一歩
不眠症は、そのタイプを理解し、適切な対処法を実践することで改善が期待できます。
今回ご紹介した4つのタイプ別対処法と生活習慣の見直しは、多くの方の睡眠改善に役立つものです。まずは自分の不眠のタイプを把握し、できることから少しずつ実践してみてください。
睡眠は健康の基盤です。良質な睡眠は、心身の健康だけでなく、日中のパフォーマンスや生活の質にも大きく影響します。不眠でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ専門家に相談することも検討してください。
私たちシモキタよあけ心療内科では、睡眠の問題を含む様々な心の悩みに対応しています。不眠でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
心地よい眠りが訪れる夜を、あなたに。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医