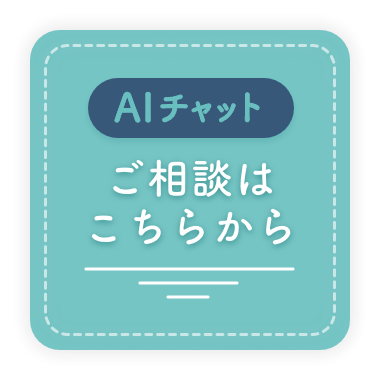2025年11月23日
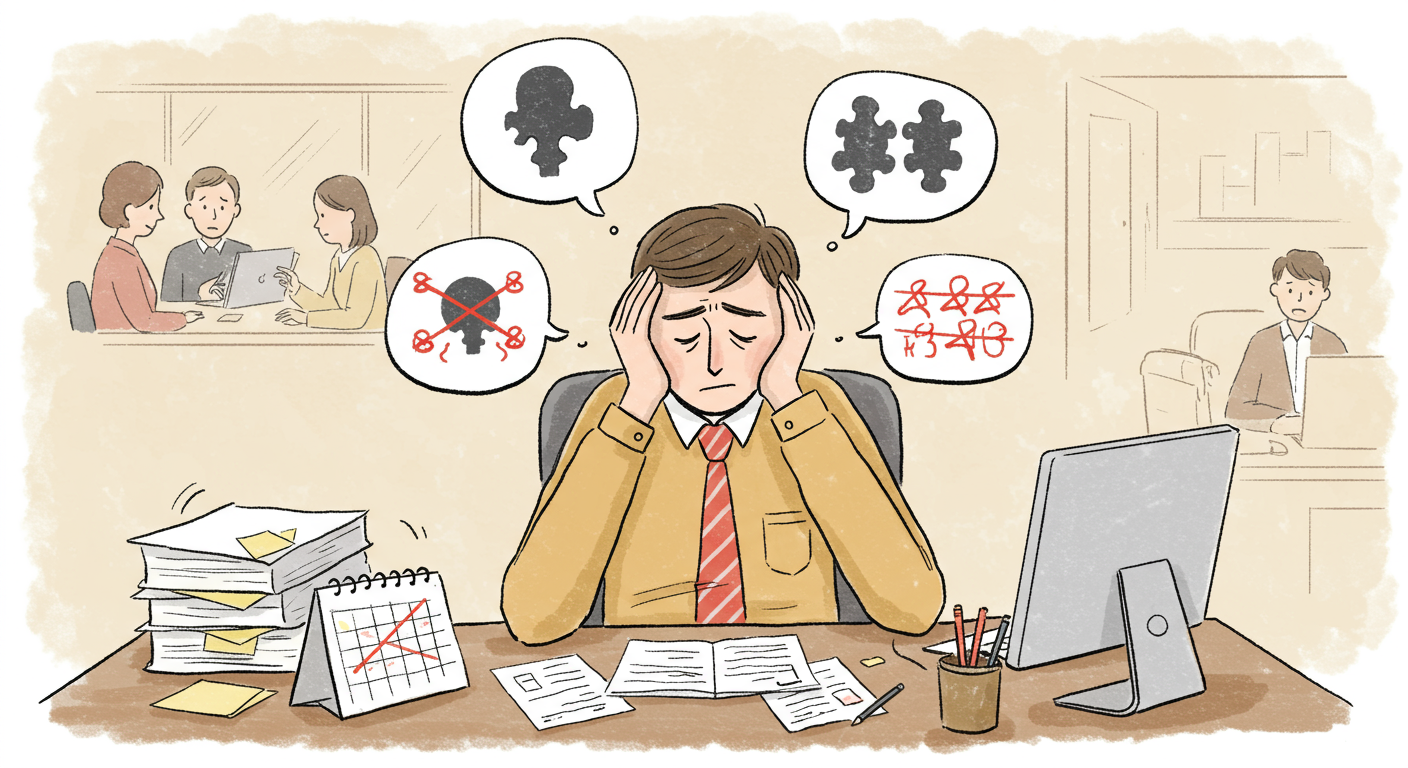
ADHDと忘れ物の関係性〜なぜ忘れ物が多くなるのか
ADHDの方が忘れ物に悩まされる理由について、まずは医学的な観点から説明します。ADHDは「注意欠如・多動症」と呼ばれる発達障害の一つです。この障害は生まれつきの脳機能の特性によるものであり、「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの特徴が現れます。
特に忘れ物の多さに直接関係するのは、「不注意」の特性です。しかし、単なる注意力の問題だけではありません。
ADHDの方の忘れ物が多い根本的な原因は、「ワーキングメモリの弱さ」にあります。

ワーキングメモリとは、情報を一時的に頭の中に保持しながら処理する能力のことです。例えば、「鍵を持った」という情報を保持しつつ、「スマホをカバンに入れる」という別の行動をする場合に使われます。
ADHDの方はこのワーキングメモリの容量が小さい傾向があります。そのため、複数のことを同時に行おうとすると、情報が「あふれ出て」しまい、忘れ物につながるのです。
私の臨床経験からも、ADHDと診断された患者さんの多くが「気をつけているのに忘れ物をしてしまう」と悩んでいます。これは怠慢や性格の問題ではなく、脳の特性によるものなのです。
ADHDによる忘れ物の具体的な困りごと
ADHDの方が日常生活で経験する忘れ物の困りごとは多岐にわたります。臨床現場でよく耳にする具体的な事例をいくつか紹介します。
まず最も多いのが「持ち物の管理が難しい」という訴えです。鍵、財布、スマホなどの必需品を頻繁に忘れたり、置き場所を忘れたりしてしまいます。
「また忘れ物をした…」と自己嫌悪に陥り、精神的な負担になっているケースも少なくありません。
学生さんの場合は、教科書やノート、提出物の忘れ物が目立ちます。宿題を完成させても提出し忘れる、必要な教材を家に置いてきてしまうといった状況が繰り返されます。
社会人の方では、会議の資料や提出書類の忘れ物、約束の時間や場所を忘れるといった問題が生じやすいです。これが仕事の評価に直結することもあり、深刻な悩みとなっています。
さらに、「そもそも重要書類などを受け取ったこと自体忘れている」「置き場所をメモしたのに、メモの存在を忘れたりメモをなくしたりしてしまう」といった二重の忘れ物も特徴的です。
このような忘れ物の繰り返しは、単なる不便さだけでなく、自己肯定感の低下や二次的な精神疾患のリスクにもつながります。だからこそ、効果的な対策が必要なのです。
ADHDの忘れ物対策10選〜専門医の視点から
ここからは、私が臨床現場で実際にADHDの患者さんに提案し、効果が確認できた忘れ物対策を10個ご紹介します。これらの方法は、ADHDの特性を理解した上で、それに合わせた工夫を取り入れたものです。
1. 「見える化」で忘れ物を防止する
ADHDの方は「目に見えないものは存在しない」と言われるほど、視覚情報に依存する傾向があります。そのため、持ち物や予定を「見える化」することが非常に効果的です。
具体的には、玄関に「持ち物チェックリスト」を貼る、透明なケースを使って中身が見えるようにする、カラフルな付箋を使って目立たせるなどの工夫が有効です。
私のクリニックに通う大学生のAさんは、玄関ドアに「財布・鍵・スマホ・交通系ICカード」と書いた付箋を貼ることで、忘れ物が激減しました。
2. 「置き場所の固定」で探す手間を省く
物の置き場所を決めて、必ず同じ場所に戻す習慣をつけることは、最も基本的かつ効果的な対策です。
例えば、玄関に鍵専用のフックを設置する、財布とスマホの定位置を決める、書類は必ず特定のファイルに入れるといった具合です。

この方法は単純ですが、「いつもここに置く」という習慣化が重要です。最初は意識的に行い、徐々に自動化していくことで効果が上がります。
3. 「自分トラップ」を仕掛ける
忘れやすい物は、「絶対に通る場所」に置いて、自分自身にトラップを仕掛ける方法も効果的です。
例えば、提出書類を玄関ドアノブにかける、翌日必要な物を靴の上に置く、スマホのアラームを鳴らすために取りに行かなければならない場所に重要な物を一緒に置くなどの工夫です。
ある会社員の患者さんは、「明日持っていくべき書類を、家の鍵と一緒に玄関に置く」ことで、提出物の忘れを防いでいます。
4. デジタルツールを活用する
スマートフォンのリマインダー機能やToDoアプリ、位置情報と連動したアラームなど、デジタルツールの活用も強力な味方になります。
特に、時間や場所に応じて通知してくれる機能は、「その瞬間に思い出す」ことを助けてくれます。
忘れ物防止に特化したアプリもあります。例えば、持ち物リストを登録しておき、外出時にチェックできるアプリや、Bluetoothタグを使って物の位置を特定できるアプリなどです。
5. 「セット化」で忘れ物を減らす
関連する物をひとまとめにして「セット」として管理する方法も有効です。
例えば、通勤セット(財布・スマホ・交通系ICカード・鍵)、書類セット(印鑑・クリップ・付箋)などをポーチやケースにまとめておくことで、一度に持ち出せるようにします。
私のクリニックに通う主婦の方は、子どもの学校行事用に「行事セット」(カメラ・ハンカチ・筆記用具・予備マスク)を専用ポーチに入れて準備しています。
6. 前日準備の習慣化
忙しい朝に準備をすると忘れ物が増えるため、前日の夜に翌日必要なものを準備する習慣をつけることが大切です。

バッグに必要なものを入れる、服を選んでおく、書類をまとめておくなど、朝の負担を減らす工夫をしましょう。
ある高校生の患者さんは、学校の時間割に合わせて教科書や体育着を前日に準備することで、朝の忘れ物が大幅に減りました。
7. 「声に出す」習慣をつける
行動する際に声に出して確認することで、記憶の定着が促進されます。
「鍵をカバンに入れた」「書類をファイルに入れた」など、行動を言葉にして声に出すことで、ワーキングメモリの補助になります。
この方法は特に効果的で、声に出すことで脳の複数の領域が活性化され、記憶の定着率が高まります。
8. 「写真記録」を活用する
物の置き場所や重要な情報をスマートフォンで撮影しておくことも、外部記憶として役立ちます。
例えば、車を停めた場所、提出済みの書類、会議のホワイトボードなど、後で必要になる可能性のある情報を写真に残しておくことで、記憶の負担を減らせます。
ビジネスパーソンの患者さんからは、「名刺交換した相手の顔と名刺を一緒に撮影しておく」という工夫も聞かれます。
9. 「ダブル確認」の習慣化
外出前や重要な場面の前に、必要なものをダブルチェックする習慣をつけることも効果的です。
チェックリストを使う、声に出して確認する、別の角度から考えて抜け漏れがないか確認するなど、複数の方法で確認することで安心感も得られます。
「3秒ルール」と呼ばれる、ドアを出る前に3秒間立ち止まって持ち物を確認する習慣も推奨されています。
10. 環境調整と周囲の理解
最後に重要なのが、環境の調整と周囲の理解です。
家族や職場の理解を得て、リマインドしてもらったり、重要な連絡は複数の手段で伝えてもらうなど、サポート体制を整えることも大切です。
また、物が多すぎる環境は混乱を招きやすいため、必要最小限の物に絞り、整理整頓を心がけることも忘れ物防止につながります。
忘れ物対策を習慣化するコツ
効果的な対策を知っても、それを継続できなければ意味がありません。ここでは、忘れ物対策を習慣化するためのコツをご紹介します。
まず大切なのは、「完璧を目指さない」ことです。ADHDの特性上、すべての対策を一度に実行するのは難しいでしょう。まずは1〜2個の対策から始め、徐々に増やしていくアプローチが効果的です。
「小さな成功体験」を積み重ねることも重要です。「今日は鍵を忘れなかった」「提出物を出せた」など、小さな成功を自分で認め、褒めることで、モチベーションを維持できます。
ADHDの方は視覚的な刺激に反応しやすいため、カラフルな付箋やアプリ、目立つ色のケースなど、「目に入りやすい工夫」を取り入れるのも効果的です。
また、忘れ物対策自体を忘れないよう、リマインダーの設定や、定期的な振り返りの時間を設けることも大切です。例えば、毎週日曜日の夜に「今週の準備」として対策を確認する時間を設けるといった工夫です。
そして何より重要なのは、自分を責めないことです。忘れ物はADHDの特性によるものであり、怠慢や性格の問題ではありません。失敗しても自分を責めず、「次はどうすれば防げるか」という前向きな視点で考えることが、長期的な改善につながります。
薬物療法と忘れ物対策の関係
ADHDの治療において、薬物療法も重要な選択肢の一つです。適切な薬物療法は、忘れ物対策の効果を高める可能性があります。
ADHDの治療薬は主に、脳内の神経伝達物質であるドパミンやノルアドレナリンの働きを調整し、注意力や集中力の維持を助ける作用があります。これにより、ワーキングメモリの機能が改善され、忘れ物が減少するケースも少なくありません。
私のクリニックでも、適切な薬物療法を開始した後、「忘れ物が減った」「物事を順序立てて考えられるようになった」という報告を多く受けています。
ただし、薬物療法だけで全ての問題が解決するわけではありません。薬の効果には個人差があり、また効果が持続する時間にも限りがあります。そのため、これまでご紹介したような環境調整や行動面での工夫と組み合わせることで、より効果的な忘れ物対策が可能になります。
薬物療法を検討する際は、必ず専門医に相談し、自分に合った治療法を見つけることが大切です。副作用や服用方法、生活への影響なども含めて、総合的に判断していく必要があります。
まとめ:ADHDの忘れ物対策は「自分に合った方法」を見つけることが鍵
ADHDによる忘れ物の多さは、脳機能の特性によるものであり、本人の怠慢や性格の問題ではありません。ワーキングメモリの弱さという特性を理解した上で、適切な対策を講じることが重要です。
今回ご紹介した10の対策は、臨床現場で実際に効果が確認されたものですが、すべての方に同じように効果があるわけではありません。ADHDの特性は人によって異なるため、自分に合った方法を見つけることが鍵となります。
まずは取り組みやすい対策から始め、徐々に習慣化していくことをお勧めします。完璧を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねていくことで、長期的な改善につながります。
また、必要に応じて薬物療法も検討し、環境調整や行動面での工夫と組み合わせることで、より効果的な対策が可能になります。
忘れ物で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、専門医や支援機関に相談することも大切です。適切な理解と支援があれば、ADHDの特性とうまく付き合いながら、充実した生活を送ることができます。
ADHDの特性は「個性」でもあります。その個性を理解し、上手に付き合っていくことで、忘れ物の悩みも少しずつ軽減していくでしょう。
忘れ物でお悩みの方は、ぜひ当院シモキタよあけ心療内科にもご相談ください。ADHDの診断や治療、日常生活の工夫についてサポートいたします。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医