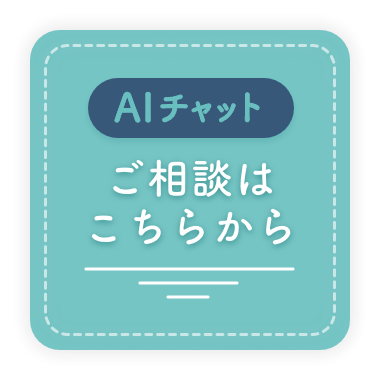2025年10月22日

うつ病で休職する際の診断書とは
うつ病で休職する際に必要となる診断書は、医師が患者の病状を証明する公的な書類です。診断書には病名や症状、治療内容や治療期間などが記載されます。会社に提出することで、正式に休職が認められ、傷病手当金などの申請にも利用できます。
診断書は単なる休みの証明ではなく、あなたの健康状態を客観的に示す医学的な証明書です。適切な診断書があることで、会社側も安全配慮義務に基づいた対応が可能になります。
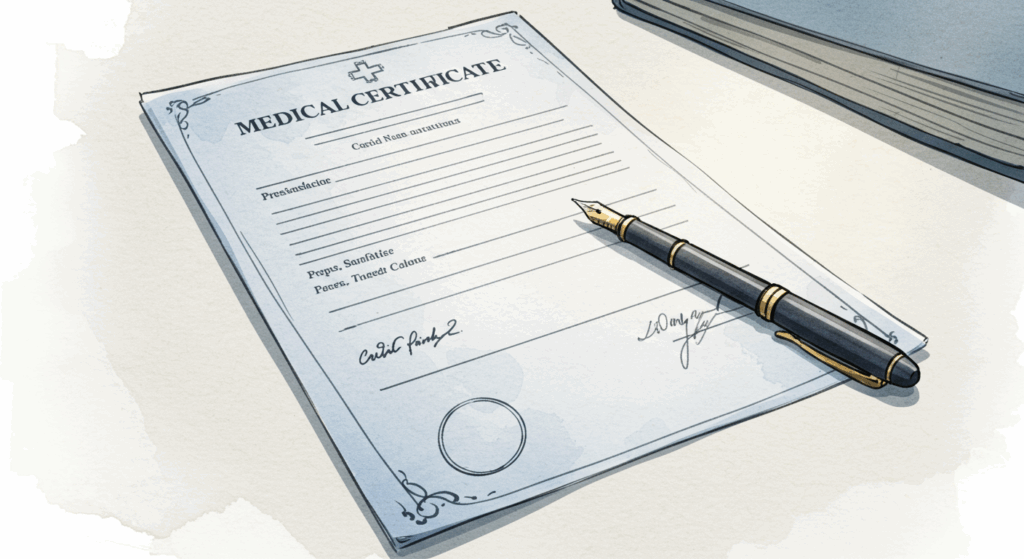
精神科医として日々多くの患者さんの診断書を作成していますが、適切な診断書があるかないかで、その後の休職生活や復職プロセスが大きく変わることを実感しています。
うつ病の診断書に記載される内容
うつ病の診断書には、主に以下のような内容が記載されます。
- 病名(うつ病、適応障害など)
- 症状の詳細
- 治療内容
- 休職の必要性と期間
- 環境調整についての見解
診断書の内容は、医師が診察結果に基づいて記載します。「いつから通院しているのか」「休職は必要なのか」「どのような治療を受けているか」などが詳しく書かれています。
特に重要なのは休職期間です。精神疾患の多くは1ヶ月以内の短期間で治らないこともあるため、治療の経過や症状に応じて適宜延長されることがあります。数ヶ月以上の期間を治療に当てる必要があると判断される場合もあります。
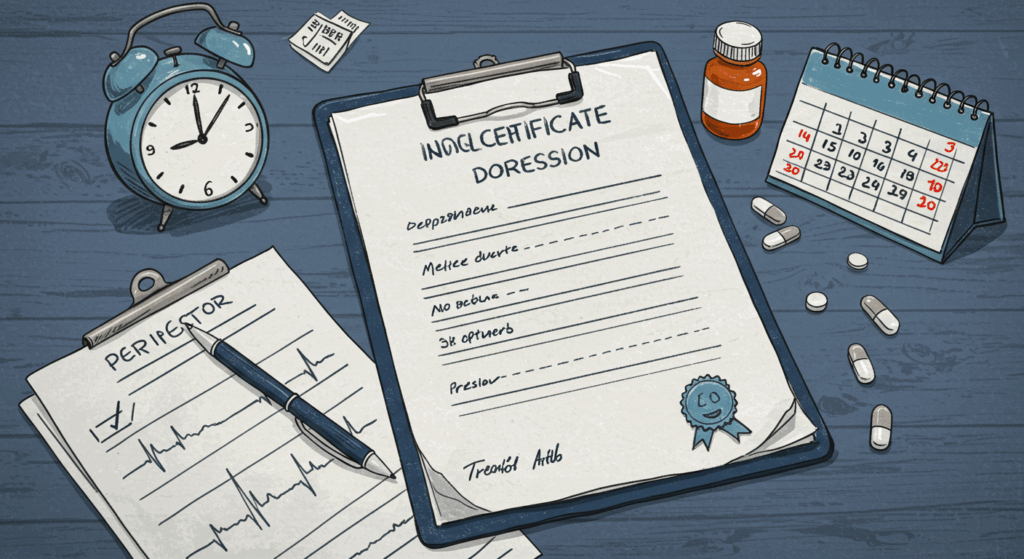
また、環境調整についての見解も重要です。「配置転換を要する」「残業は不可」「〇〇の作業は控えるのが望ましい」など、患者さんの症状や状況から適切な職場環境に変更するよう会社側に指示・アドバイスすることもあります。
うつ病の診断書はすぐにもらえるのか
うつ病の診断書がすぐにもらえるかどうかは、症状の重さやクリニックの方針によって異なります。早急に休職が必要だと判断された場合や、一度の診断でうつ病と断定できる場合は、初診日でも診断書をもらえることがあります。
しかし、以下のようなケースでは診断書をすぐにもらえないこともあります。
- 一度の診断ではうつ病と断定できない場合
- 休職が必要だと判断できず、しばらく症状の経過をみる必要がある場合
- クリニックの方針で診断書の即日発行に対応していない場合
症状が曖昧で、一度の診断ではうつ病と判断できない場合は、診断書をすぐにもらえません。症状が軽く休職が必要ないと判断した際も診断書が発行されず、症状の経過をチェックしたうえで再検査となるケースもあります。

私の臨床経験では、明らかにうつ症状が重く、すぐに休養が必要だと判断できる場合は初診でも診断書を発行することがあります。しかし、症状が複雑で判断が難しい場合は、2〜3回の診察を経てから診断書を発行することもあります。
患者さんの中には「すぐに診断書が欲しい」と希望される方もいますが、正確な診断のためにも、医師の判断を尊重することが大切です。
うつ病の診断書をもらうための伝え方
うつ病の診断書をスムーズにもらうためには、医師に症状を適切に伝えることが重要です。以下のポイントを意識して診察に臨みましょう。
日常生活で困っていることを具体的に伝える
「眠れない」「食欲がない」といった症状だけでなく、「朝起きられず会社に行けない」「集中力が続かず仕事のミスが増えた」など、日常生活や仕事でどのように困っているかを具体的に伝えましょう。
うつ病の症状は人によって現れ方が異なります。あなたが実際に感じている苦痛や困難を、自分の言葉で伝えることが大切です。
症状のメモを準備する
診察時は緊張してうまく話せないこともあります。事前に「どのような症状があるのか」「日常生活で困っていること」などをメモに書いておくと、伝えやすくなります。
書いてきたメモを読みながら伝えたり、話すのも緊張するときは先生にそのままメモを渡してみるのもよいでしょう。
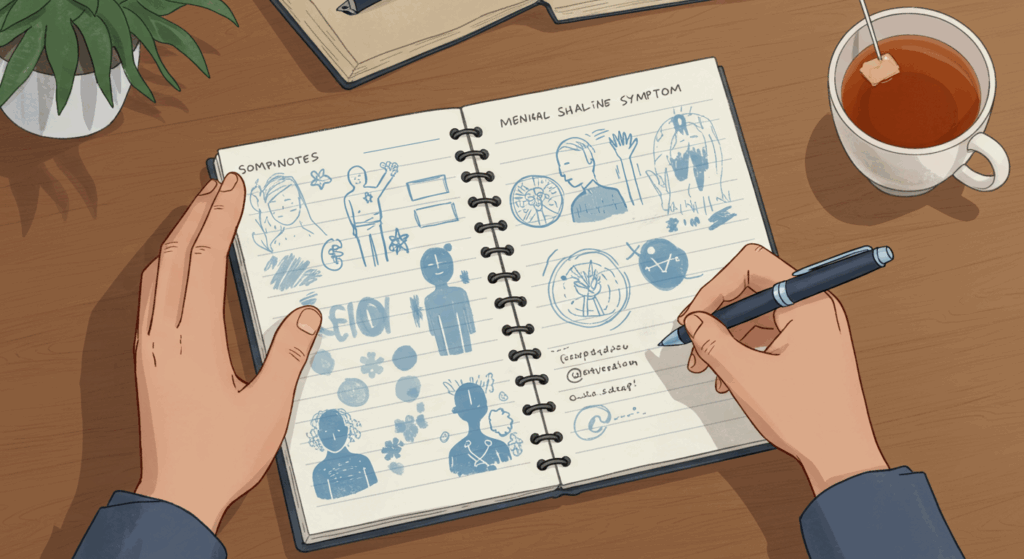
診断書が必要な理由を伝える
なぜ診断書が必要なのかを医師に伝えることも大切です。「会社を休職するため」「傷病手当金の申請のため」など、具体的な理由を説明しましょう。
診断書の用途によって記載内容が異なることもあるため、用途を明確に伝えることで、適切な診断書を作成してもらえます。
うつ病の診断書が発行される症状例
どのような症状があると診断書が発行されるのでしょうか。実際の臨床現場で見られる症状例をご紹介します。
職場でのストレスによるうつ症状
職場内でのトラブルや過度な業務負担が原因で、以下のような症状が現れている場合は、うつ病の診断書が発行されることがあります。
- 朝起きられなくなり、身体が動かなくなる
- 業務に集中できなくなる
- 強い自殺願望がある
- 会社へ行きたくないと感じ、事故に巻き込まれたいと日々考える
上司からの執拗な嫌がらせや、無茶な業務量などのパワハラに悩んでいる方は、ネガティブな思考により眠れない、食事がおいしく感じない、集中力が続かないなどの症状が出て、仕事への意欲がなくなり自殺願望を抱くこともあります。
身体症状を伴ううつ状態
うつ病は精神症状だけでなく、様々な身体症状を伴うことがあります。以下のような症状が見られる場合も診断書が発行されることがあります。
- 不眠や過眠が続いている
- 食欲不振や過食が続いている
- 原因不明の頭痛や腹痛、めまいがある
- 極度の疲労感があり、日常生活に支障がある
身体症状が前面に出ているケースでは、患者さん自身が「うつ病かもしれない」と認識していないこともあります。しかし、これらの身体症状がうつ病から来ていると医師が判断した場合は、診断書が発行されることがあります。
うつ病の診断書に関する注意点
診断書の費用について
診断書の発行には費用がかかります。一般的な病院作成の形式をとった診断書の費用は数千円程度ですが、その他特殊な記載方法や用途に応じて料金の幅が多少あります。特殊な場合には、症状の内容に応じて記載する内容が増えるため、費用に幅が出てきます。
診断書の発行は診療行為ではないため健康保険が適用されず、全額自己負担となります。医療機関によって価格が異なるため、事前に電話などで確認しておくと安心です。
診断書だけでは休職できないケースも
診断書があれば必ず休職できるわけではありません。会社の就業規則に休職制度がない場合や、休職要件を満たしていない場合は、診断書があっても休職が認められないことがあります。
また、診断書の内容が会社の休職基準を満たしていない場合も、休職が認められないことがあります。休職を希望する場合は、事前に会社の休職制度について確認しておくことをおすすめします。
診断書の記載内容と実際の症状の一致
診断書の内容は、実際の症状と一致している必要があります。症状を誇張して伝えたり、実際にない症状を訴えたりすると、適切な治療が受けられないだけでなく、後々のトラブルの原因になることもあります。
医師は患者さんの訴えをもとに診断を行いますが、経験豊富な医師は症状の整合性なども見ています。正直に症状を伝え、適切な診断と治療を受けることが大切です。
うつ病で休職する際の手続きの流れ
うつ病で休職する際の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 精神科や心療内科を受診し、診断を受ける
- 医師から診断書を発行してもらう
- 会社に診断書を提出し、休職を申請する
- 会社の規定に従って休職手続きを進める
- 必要に応じて傷病手当金などの申請を行う
会社によって休職制度や手続きは異なりますので、人事部や上司に確認することをおすすめします。また、産業医がいる会社では、産業医に診断書を提出し、職場環境の調整について相談することもできます。
休職中も定期的に通院し、症状の経過を医師に伝えることが大切です。復職の際にも診断書が必要になることがありますので、医師と相談しながら進めていきましょう。
うつ病で休職中に利用できる制度
うつ病で休職中は、以下のような制度を利用できる可能性があります。
傷病手当金
健康保険に加入している方が、病気やケガのために会社を休み、給与を受けられない場合に支給される制度です。支給額は、直近12ヶ月の平均給与の約3分の2で、最長1年6ヶ月支給されます。
申請には医師の診断書が必要です。会社の給与担当者や健康保険組合に相談し、必要な手続きを行いましょう。
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患で通院している方が利用できる制度で、医療費の自己負担が軽減されます。通常3割の自己負担が1割になりますが、所得に応じて月額上限があります。
申請には医師の診断書が必要です。お住まいの市区町村の窓口で申請手続きを行います。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方が取得できる手帳です。等級は1級から3級まであり、税金の控除や公共料金の割引などの優遇措置を受けられます。
申請には医師の診断書または精神障害による障害年金を受給している場合はその証書等の写しが必要です。初診日から6ヶ月以上経過していることが条件となります。
まとめ:適切な診断書で安心して休養を
うつ病の診断書は、あなたの健康状態を客観的に証明する重要な書類です。適切な診断書があることで、会社を正式に休職し、必要な支援制度を利用することができます。
診断書をもらうためには、医師に症状を正直に伝えることが大切です。日常生活でどのように困っているかを具体的に説明し、診断書が必要な理由も明確に伝えましょう。
診断書の発行には費用がかかり、すぐに発行されない場合もありますが、正確な診断のためにも医師の判断を尊重することが大切です。
うつ病は適切な休養と治療によって回復する病気です。診断書を活用して十分な休養を取り、専門医の指導のもとで治療を続けることで、心身の健康を取り戻しましょう。
メンタルヘルスの不調を感じたら、早めに専門医に相談することをおすすめします。シモキタよあけ心療内科では、うつ病をはじめとする様々な精神疾患に対応し、休職・復職のサポートも行っています。お気軽にご相談ください。
詳しい情報や予約方法については、シモキタよあけ心療内科の公式サイトをご覧ください。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医