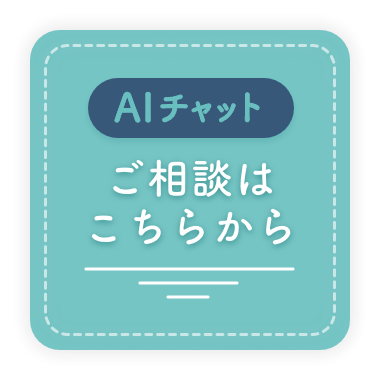2025年9月29日

睡眠障害の症状と受診の必要性
夜になっても眠れない。朝になってもすっきり目覚められない。日中、強い眠気に襲われる。このような症状に悩まされていませんか?
睡眠障害は現代社会において非常に多くの方が抱える問題です。単なる「寝不足」と軽視されがちですが、放置すると身体的・精神的健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
睡眠障害には不眠症、睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシーなど様々な種類があります。症状も多岐にわたるため、「どの診療科を受診すべきか」と迷われる方も多いでしょう。
私は精神科専門医として多くの睡眠障害患者さんを診てきました。適切な診療科選びが早期改善への第一歩です。この記事では、睡眠障害の種類別に最適な受診先をご紹介します。
睡眠障害の主な種類と特徴
まず、代表的な睡眠障害とその特徴について理解しましょう。症状を正しく把握することが、適切な診療科選びにつながります。
睡眠障害は大きく分けて以下のようなタイプに分類されます。あなたの症状がどれに当てはまるか確認してみてください。
不眠症
不眠症は最も一般的な睡眠障害です。寝つきが悪い「入眠障害」、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」、予定より早く目覚めてしまう「早朝覚醒」、十分な時間寝ても疲れが取れない「熟眠障害」などの症状があります。
ストレスや不安、うつ病などの精神疾患が原因となることも多く、生活習慣の乱れも大きく影響します。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に呼吸が一時的に止まる状態を繰り返す障害です。大きないびきや日中の強い眠気が特徴的です。
睡眠中の無呼吸により血中酸素が低下し、高血圧や心疾患などの合併症リスクが高まります。肥満の方や首回りが太い方に多く見られます。
過眠症(特発性過眠症、ナルコレプシーなど)
十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、日中に強い眠気に襲われる障害です。ナルコレプシーでは感情が高ぶった時に突然力が抜ける「情動脱力発作」を伴うこともあります。
思春期から若年成人に発症することが多く、日常生活に大きな支障をきたします。
概日リズム睡眠障害
体内時計の乱れによって、社会的に望ましい時間帯に眠れなくなる障害です。「睡眠相後退症候群」では就寝・起床時間が遅くなり、「睡眠相前進症候群」では極端に早く寝て早く起きるようになります。
特に10代後半から20代に多く見られ、不登校や社会適応の問題につながることもあります。
睡眠障害は何科を受診すべきか?
睡眠障害の症状や原因によって、最適な受診先は異なります。ここでは症状別に適切な診療科をご紹介します。
不眠症の場合
不眠症状がある場合は、まず精神科・心療内科の受診をおすすめします。不眠の背景には、うつ病や不安障害などの精神疾患が隠れていることも少なくありません。
精神科専門医は睡眠薬の適切な処方だけでなく、不眠の原因となる精神的問題にも対応できます。また、睡眠習慣の改善指導や認知行動療法なども行います。
最近では睡眠障害に特化した「睡眠外来」を設けている医療機関も増えています。睡眠専門医がいる医療機関であれば、より専門的な診療が受けられるでしょう。
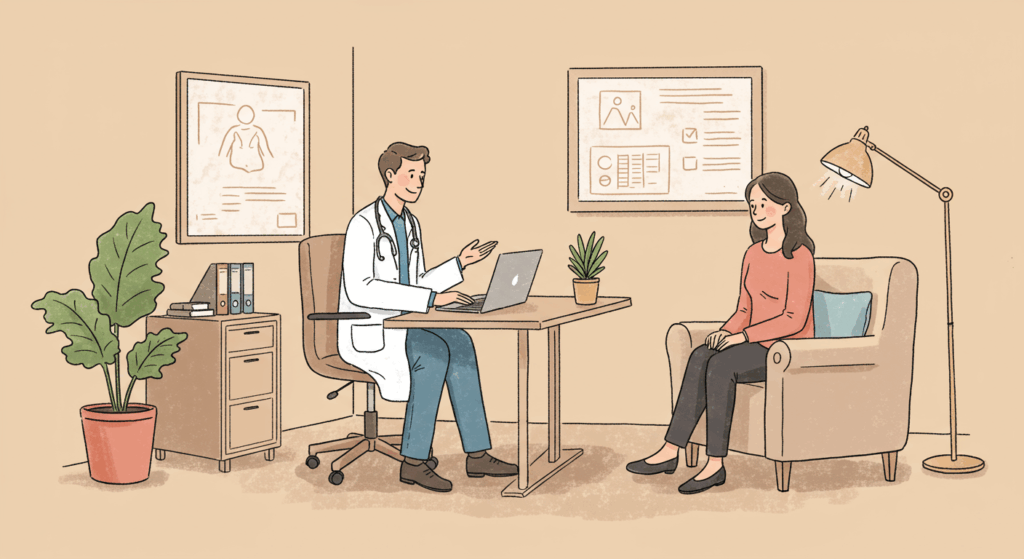
どうしても精神科に抵抗がある場合は、内科でも不眠症の診療は可能です。ただし、複雑な不眠症状の場合は、最終的に精神科や睡眠専門医への紹介となることが多いです。
睡眠時無呼吸症候群の場合
大きないびきや睡眠中の呼吸停止、日中の強い眠気がある場合は、呼吸器内科または耳鼻咽喉科の受診が適切です。
呼吸器内科では睡眠時無呼吸症候群の診断検査や、CPAP(持続陽圧呼吸療法)などの治療を行います。一方、耳鼻咽喉科では気道閉塞の原因となる鼻や咽頭の問題を評価し、必要に応じて手術治療も検討します。
肥満が原因と考えられる場合は、循環器内科や糖尿病内科など、生活習慣病を専門とする診療科も選択肢となります。
過眠症(特発性過眠症、ナルコレプシーなど)の場合
日中に強い眠気が続く場合は、脳神経内科または精神科の受診をおすすめします。特にナルコレプシーなどの中枢性過眠症は、脳内の神経伝達物質の異常が関係しているため、専門的な診断と治療が必要です。
過眠症の正確な診断には、睡眠ポリグラフ検査や反復睡眠潜時検査などの精密検査が必要になることがあります。シモキタよあけ心療内科(当院)では、これらの検査を行っていないため、これらの検査ができる日本睡眠学会認定の専門医療機関を選ぶとよいでしょう。
概日リズム睡眠障害の場合
体内時計の乱れによる睡眠リズムの問題は、精神科・心療内科での受診が適切です。特に思春期・青年期の睡眠相後退症候群(昼夜逆転)は、不登校や社会適応の問題と関連していることも多いため、精神科医による包括的な評価が重要です。
治療には生活習慣の改善指導や光療法、メラトニン受容体作動薬などの薬物療法が用いられます。
子どもの睡眠障害はどうする?
子どもの睡眠問題は、発達や学校生活に大きな影響を与えます。では、子どもの睡眠障害はどの診療科を受診すべきでしょうか。
15歳以下の子どもの場合は、基本的に小児科を受診するのが適切です。小児科医は子どもの発達段階に応じた睡眠の問題に対応できます。

中学生や高校生で睡眠リズムの乱れや不登校がある場合は、児童精神科の受診も検討すべきです。この年代では、睡眠相後退症候群や起立性調節障害、発達障害などが睡眠問題の背景にあることも少なくありません。
子どもの大きないびきや睡眠時の呼吸停止が気になる場合は、小児科または耳鼻咽喉科を受診しましょう。小児の睡眠時無呼吸の原因として、扁桃肥大やアデノイド肥大などが考えられます。
睡眠専門医療機関の選び方
より専門的な診療を受けたい場合は、睡眠障害に特化した医療機関を選ぶことも一つの選択肢です。
日本睡眠学会認定の専門医療機関
日本睡眠学会では、睡眠障害の診療に必要な設備や人材を備えた医療機関を「専門医療機関」として認定しています。特にA型認定施設では、終夜睡眠ポリグラフ検査や反復睡眠潜時検査など、高度な睡眠検査が可能です。
専門医療機関は日本睡眠学会のウェブサイトで検索できます。お住まいの地域で探してみるとよいでしょう。
睡眠外来のある病院・クリニック
最近では「睡眠外来」や「睡眠センター」を設けている医療機関も増えています。これらの施設では、複数の診療科の医師が連携して睡眠障害の診療にあたることが多いです。
例えば、国立精神・神経医療研究センター病院では、日本睡眠学会総合専門医による診断・治療、専門検査技師による検査、臨床心理士による不眠症の認知行動療法などを行っています。
愛知医科大学病院の睡眠医療センターでは、睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー、むずむず脚症候群、レム睡眠行動障害など、幅広い睡眠障害の診療を行っています。
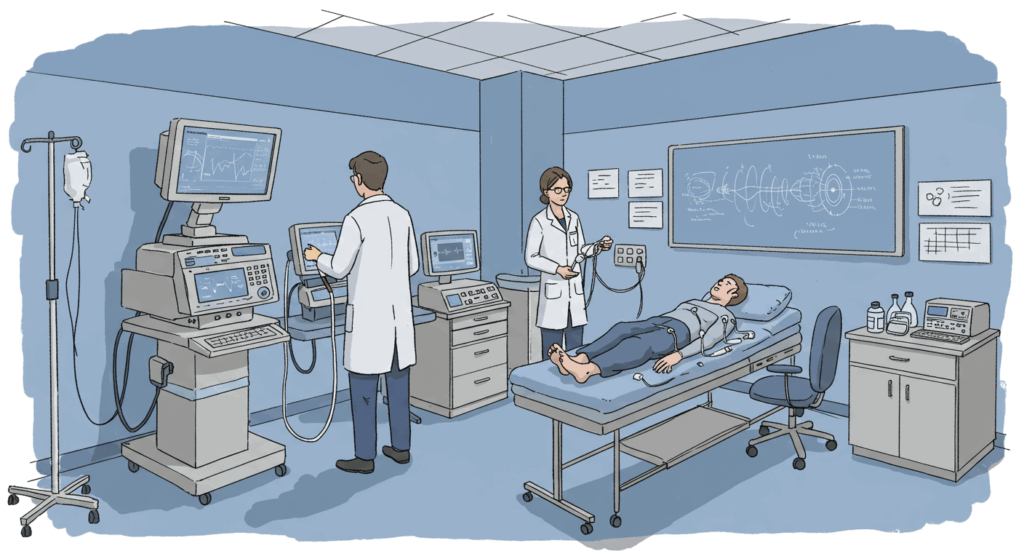
睡眠障害の診断と治療の流れ
睡眠障害の診療は、どのような流れで進むのでしょうか。医療機関を受診する際の参考にしてください。
初診時の問診と検査
初診では、睡眠に関する詳しい問診が行われます。睡眠の状態、生活習慣、既往歴、服用中の薬などについて質問されます。
多くの医療機関では、事前に睡眠日誌をつけるよう指示されることもあります。1〜2週間の睡眠パターンを記録することで、より正確な診断につながります。
問診の後、必要に応じて血液検査や心電図検査などの一般的な検査が行われます。睡眠障害の種類によっては、さらに専門的な検査が必要になることもあります。
睡眠検査の種類
睡眠障害の診断には、以下のような専門的な検査が用いられることがあります。
終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)
睡眠中の脳波、眼球運動、筋電図、心電図、呼吸状態、血中酸素濃度などを同時に測定する検査です。睡眠時無呼吸症候群やレム睡眠行動障害などの診断に不可欠です。
検査は通常、医療機関に一泊して行います。費用は健康保険を使用して3割負担の場合、約5万円程度かかることが多いです。
反復睡眠潜時検査(MSLT検査)
日中の眠気を客観的に評価する検査です。2時間おきに20分間の仮眠をとり、眠りに落ちるまでの時間を測定します。ナルコレプシーなどの過眠症の診断に用いられます。
通常、PSG検査の翌日に行われ、両方の検査を合わせると6万円程度(3割負担の場合)かかることがあります。
治療方法の選択
診断が確定したら、睡眠障害の種類や重症度に応じた治療が始まります。
不眠症の治療
不眠症の治療では、睡眠薬の処方だけでなく、睡眠衛生指導(規則正しい生活習慣の確立)や認知行動療法なども重要です。特に認知行動療法は、長期的な効果が期待できる治療法として注目されています。
睡眠時無呼吸症候群の治療
睡眠時無呼吸症候群の標準治療は、CPAP(持続陽圧呼吸療法)です。睡眠中にマスクを装着し、一定の圧力で空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぎます。
軽症から中等症の場合は、マウスピース(口腔内装置)も選択肢となります。また、肥満が原因の場合は減量指導も行われます。
過眠症の治療
ナルコレプシーなどの過眠症には、中枢神経刺激薬などの薬物療法が中心となります。日中の計画的な仮眠も症状改善に役立つことがあります。
概日リズム睡眠障害の治療
概日リズム睡眠障害には、生活習慣の改善、光療法、メラトニン受容体作動薬などが用いられます。特に重症の睡眠相後退症候群では、入院による治療が必要になることもあります。
睡眠障害治療の実際と専門医の役割
精神科専門医として多くの睡眠障害患者さんを診てきた経験から、治療の実際と専門医の役割についてお伝えします。
薬物療法だけに頼らない総合的アプローチ
睡眠障害の治療では、薬物療法だけに頼るのではなく、生活習慣の改善や認知行動療法などを組み合わせた総合的なアプローチが重要です。
専門医は睡眠薬の適切な選択と用量調整だけでなく、患者さん一人ひとりの生活背景や心理的要因を考慮した治療計画を立てます。
例えば、不眠症の患者さんには、就寝時間を一定にする、寝室の環境を整える、就寝前のカフェイン摂取を避けるなど、具体的な睡眠衛生指導を行います。
継続的なフォローアップの重要性
睡眠障害の治療は一朝一夕には完結しません。特に慢性不眠症や睡眠時無呼吸症候群では、長期的な治療とフォローアップが必要です。
定期的な通院を通じて、治療効果の評価や副作用のチェック、生活習慣の見直しなどを行います。患者さんとの信頼関係を築きながら、継続的に支援していくことが専門医の重要な役割です。
まとめ:適切な診療科選びが睡眠障害改善の第一歩
睡眠障害の種類によって最適な受診先は異なります。症状に応じた適切な診療科を選ぶことが、早期改善への近道です。
不眠症には精神科・心療内科、睡眠時無呼吸症候群には呼吸器内科や耳鼻咽喉科、過眠症には脳神経内科や精神科、概日リズム睡眠障害には精神科・心療内科が適しています。子どもの睡眠障害は小児科や児童精神科を受診しましょう。
より専門的な診療を希望する場合は、日本睡眠学会認定の専門医療機関や睡眠外来のある医療機関を選ぶとよいでしょう。
睡眠は健康の基盤です。睡眠の問題を抱えたまま我慢せず、ぜひ専門医に相談してください。適切な診断と治療により、多くの睡眠障害は改善が期待できます。
当院シモキタよあけ心療内科でも、不眠症をはじめとする様々な睡眠障害の診療を行っています。睡眠でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
詳しい情報はシモキタよあけ心療内科の公式サイトをご覧ください。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医