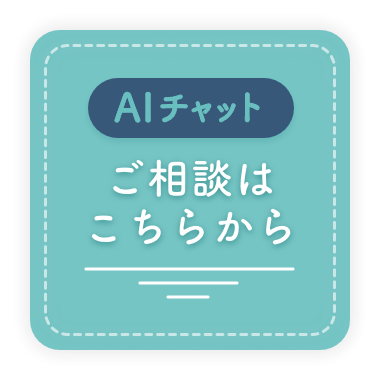2025年9月15日
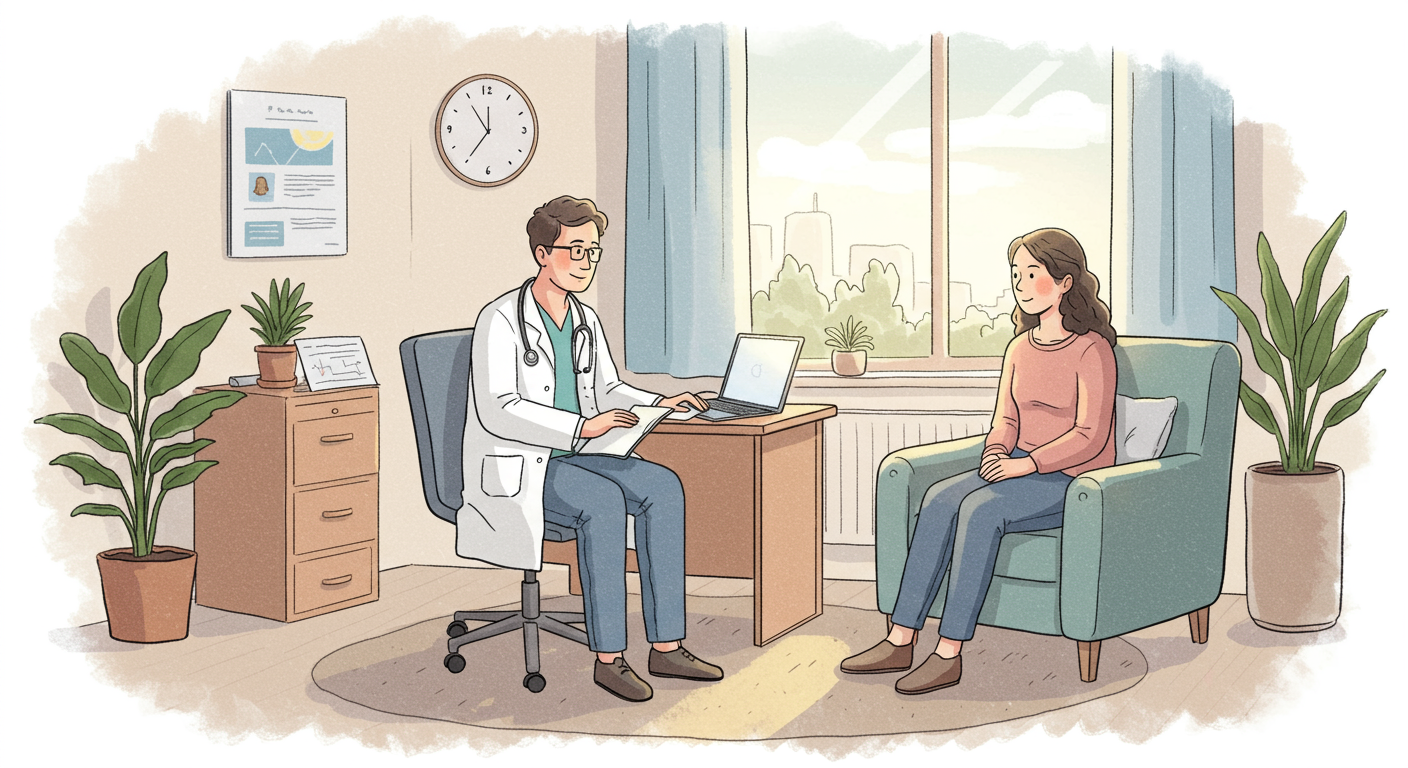
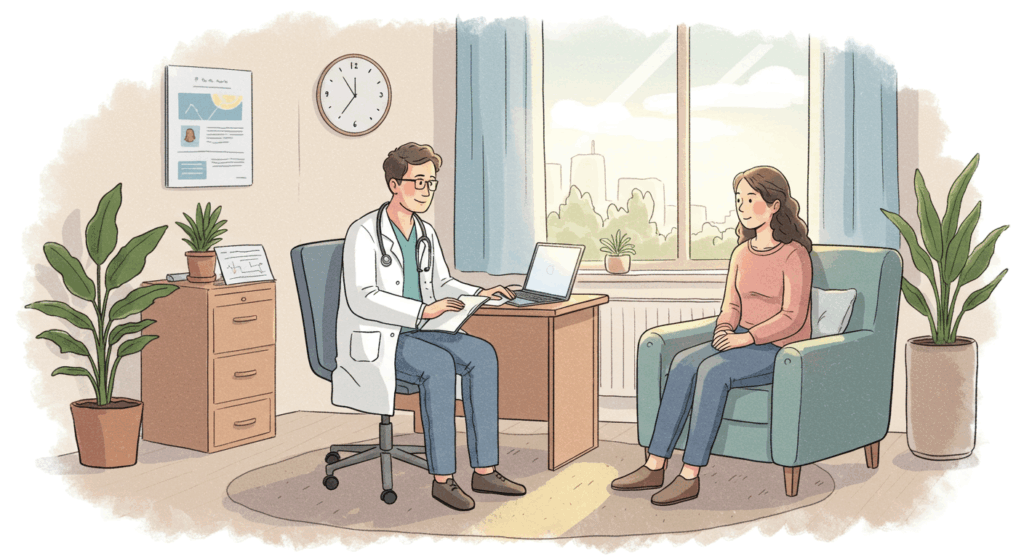
ADHDとは?基本的な理解から始めよう
ADHDは「注意欠如・多動症」(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)の略称です。発達障害の一種であり、年齢に見合わない不注意や多動性、衝動性を主な特徴とする症状です。
「なんとなく聞いたことはあるけど、詳しくは知らない」という方も多いのではないでしょうか。
ADHDは先天的な脳の機能の違いによって生じる状態で、子どもだけでなく大人にも見られます。脳内の神経伝達物質のバランスや前頭葉の機能に関係していると考えられていますが、明確な原因はまだ解明されていません。
ADHDの有病率は、子どもでは約5%、大人では約2.1%(50人に1人程度)と言われています。決して珍しい状態ではありません。
多くの方が「ADHD=子どもに多い症状」と考えがちですが、大人になってから診断される方も少なくありません。子ども時代に症状があったものの、診断されずにそのまま過ごしてきた方が、大人になって初めて気づくケースも多いのです。
私が精神科医として診療していると、「学生時代はなんとか乗り切れたけど、社会人になって仕事や人間関係で困難を感じるようになった」という相談をよく受けます。これはADHDの特性が、社会的要求の高まりによって顕在化したケースかもしれません。
では、ADHDの特徴とはどのようなものなのでしょうか?次のセクションで詳しく見ていきましょう。
ADHDの3つの主要症状
ADHDには「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの主要な特徴があります。これらの特徴は、同時にすべて現れるわけではなく、人によって表れ方が異なります。
それぞれの特徴について、具体的に見ていきましょう。
不注意の特徴
不注意とは、注意を持続することや集中することが難しい状態を指します。以下のような特徴が見られます:
- 細部に注意が向かず、ケアレスミスが多い
- 課題や活動に集中し続けることが難しい
- 話しかけられても聞いていないように見える
- 指示に従えず、課題や活動をやり遂げられない
- 課題や活動を順序立てて行うことが苦手
- 集中を要する課題を避ける、嫌がる
- 活動に必要な物をよく失くす(鍵、書類、スマホなど)
- 外部からの刺激で簡単に注意がそれる
- 日常的な活動をよく忘れる(約束、用事など)
これらの特徴は、学校や職場での作業効率に大きく影響します。特に大人のADHDでは、不注意の症状が目立つことが多いです。
多動性の特徴
多動性とは、年齢や状況に不相応な落ち着きのなさや過度な身体的活動を指します。以下のような特徴が見られます:
- 手足をそわそわ動かしたり、着席中もじっとしていられない
- 座っていることを求められる状況で席を離れてしまう
- 不適切な状況で走り回ったり高いところによじ登ったりする(大人では内的な落ち着きのなさとして現れることも)
- 静かに遊んだり余暇活動に参加することが難しい
- じっとしていられず、常に「エンジンで動かされている」ように活動的
- 過度にしゃべる
子どもの頃は多動性が目立つことが多いですが、大人になるにつれて目立たなくなることもあります。これは多動が好ましくない行為だと学習し、自ら規制するようになるためです。
衝動性の特徴
衝動性とは、考える前に行動してしまう傾向を指します。以下のような特徴が見られます:
- 質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう
- 順番を待つことが難しい
- 他者を妨害したり、会話や活動に割り込んだりする
- 思いついたことをすぐに口にしたり行動に移したりする
衝動性は、特に対人関係においてトラブルの原因となることがあります。考えなしに発言してしまい、後で後悔するというパターンが繰り返されることもあるでしょう。
これらの3つの特徴は、ADHDの人によって異なる組み合わせで現れます。また、年齢によっても症状の現れ方が変化することがあります。
ADHDの特徴をどのように理解すれば良いのでしょうか?
大切なのは、これらの特徴を「個性」として捉える視点です。ADHDの特性には、ネガティブな面だけでなく、ポジティブな面もたくさんあります。例えば、「物事をやり遂げることができない」という特徴は、「切り替えが早い」というポジティブな面もあります。
次のセクションでは、ADHDの診断基準について詳しく見ていきましょう。
ADHDの診断基準
ADHDの診断は、アメリカ精神医学会(APA)の「精神疾患・精神障害の診断・統計マニュアル第5版」(DSM-5)に基づいて行われます。診断には、以下の条件を満たす必要があります。
ADHDと診断されるためには、不注意や多動性・衝動性の症状が、同年齢の発達水準に比べて明らかに強く、日常生活に支障をきたしている必要があります。
DSM-5に基づく診断基準
DSM-5では、以下の5つの条件をすべて満たした場合にADHDと診断されます:
- 「不注意」と「多動-衝動性」が同程度の年齢の発達水準に比べてより頻繁に強く認められること
- 症状のいくつかが12歳以前より認められること
- 2つ以上の状況において(家庭、学校、職場、その他の活動中など)障害となっていること
- 発達に応じた対人関係や学業的・職業的な機能が障害されていること
- その症状が、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中に起こるものではなく、他の精神疾患ではうまく説明されないこと
これらの基準は、子どもと大人の両方に適用されます。ただし、大人の場合は症状の現れ方が異なることがあるため、診断には専門的な知識と経験が必要です。
ADHDの診断プロセス
ADHDの診断には、絶対的な数値基準はなく、専用の医学的検査も確立されていません。そのため、問診や心理検査を通じて総合的に診断を行います。
診断の流れは以下のようになります:
- 問診:現在の症状や悩み、生活の様子について医師が聞き取ります。発達障害では自覚がないケースもあるため、家族や周囲の意見も重要な判断材料となります。
- 心理検査:医療機関により検査方法は異なります。一般に、子ども向けには「ADHD-RS」や「Conners 3 日本語版」、大人向けには「CAARS」などの心理検査を使用し、症状の傾向を客観的に把握します。必要に応じて、知能検査(WAIS-Ⅳなど)や発達検査も併用されます。
- 診断基準の確認:DSM-5に基づき、症状が継続しているか、生活に支障が出ているかなどの条件を確認します。
問診時には、以下のような情報を準備しておくと診断がスムーズに進みます:
- 学校時代の行動やエピソード
- 職場での困りごと(遅刻、作業ミスなど)
- 過去の疾患歴(うつ病、てんかんなど)
- 成長過程に関する情報(成績、母子手帳など)
- ADHDセルフチェック(ASRS-v1.1など)の結果
ADHDの診断は非常に慎重に行われます。似たような症状を示す他の精神疾患や発達障害との区別も重要です。そのため、専門医による総合的な判断が不可欠となります。
私の臨床経験では、「自分はADHDではないか」と思って受診される方が増えています。しかし、インターネット上の情報だけで自己診断するのではなく、専門医の診察を受けることが大切です。
次のセクションでは、子どものADHDと大人のADHDの違いについて詳しく見ていきましょう。
子どものADHDと大人のADHDの違い
ADHDは子どもの頃から存在する発達障害ですが、年齢によって症状の現れ方が異なります。子どもと大人では、どのような違いがあるのでしょうか。
成長とともに脳の発達や環境への適応力が変化するため、ADHDの特徴も変化していきます。特に大人になると、子どもの頃とは異なる形で症状が現れることがあります。
子どものADHDの特徴
子どものADHDでは、以下のような特徴が見られることが多いです:
- 多動性が目立つ:教室で席を離れる、絶えず動き回る、高いところによじ登るなど、身体的な多動性が顕著
- 学業への影響:授業に集中できない、宿題を忘れる、指示に従えないなどの問題が生じる
- 友人関係の困難:順番を待てない、会話に割り込む、ルールを守れないなどで対人関係に問題が生じることがある
- 感情のコントロールが難しい:イライラしやすい、かんしゃくを起こしやすい
子どものADHDは、特に学校生活において困難を抱えることが多いです。教室という構造化された環境で静かに座って授業を聞くことや、順序立てて課題に取り組むことが求められるため、ADHDの特性が目立ちやすくなります。
大人のADHDの特徴
大人のADHDでは、以下のような特徴が見られることが多いです:
- 不注意が中心:多動性は目立たなくなり、不注意の症状が前面に出ることが多い
- 内的な落ち着きのなさ:外から見える多動性は減少するが、内面的な落ち着きのなさ(貧乏ゆすり、足を頻繁に組みなおすなど)として現れる
- 仕事上の問題:締め切りを守れない、優先順位をつけられない、書類をなくす、ミスが多いなど
- 時間管理の困難:遅刻が多い、予定を忘れる、時間の見積もりが甘いなど
- 対人関係の問題:衝動的な発言で誤解を招く、感情のコントロールが難しく対立が生じやすいなど
- 自己管理の困難:整理整頓ができない、金銭管理が苦手、生活リズムが乱れやすいなど
大人のADHDは、職場や家庭など複雑な社会的状況で困難を抱えることが多いです。責任が増し、自己管理が求められる環境で、ADHDの特性がより顕著になることがあります。
大人のADHDの症状の具体例としては、以下のようなものが挙げられます:
- ケアレスミスが多い
- 口頭だけだと上司からの指示が頭に残らない
- 電話を受けて誰からの電話か聞き忘れる
- 事務作業で金額やデータを間違って入力する
- 段取りに従って行動できない
- 約束を忘れがち
- 会議に集中できない
- 会議中に貧乏ゆすりなどで体が動く
- デスクワークで座っているのが苦痛
- 同僚との会話で興奮しやすい
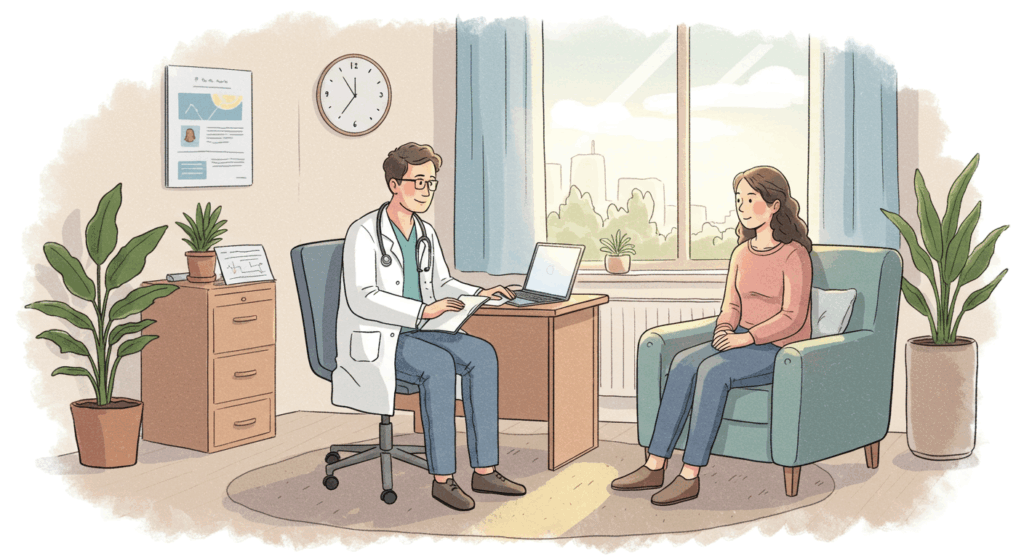
大人になってから初めてADHDと診断されるケースも少なくありません。子どもの頃は何とか対処できていたものの、社会人になって責任が増し、複雑な業務を求められるようになったことで、ADHDの特性が顕在化することがあります。
あなたは、これらの症状に心当たりはありますか?
次のセクションでは、ADHDの治療法について詳しく見ていきましょう。
ADHDの治療法
ADHDの治療は、薬物療法と非薬物療法(心理社会的治療)を組み合わせた包括的なアプローチが効果的です。個人の症状や生活状況に合わせて、最適な治療法を選択することが重要です。
治療の目標は、ADHDの症状を軽減し、日常生活の質を向上させることにあります。完全に「治す」というよりも、ADHDの特性と上手に付き合いながら、自分らしく生きていくことを目指します。
薬物療法
ADHDの薬物療法では、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンのバランスを調節する薬剤が使用されます。主な薬剤には以下のようなものがあります:
- メチルフェニデート製剤:中枢神経刺激薬の一種で、脳内のドーパミンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害することで、これらの神経伝達物質の濃度を高めます。
- アトモキセチン:非中枢神経刺激薬で、ノルアドレナリンの再取り込みを選択的に阻害します。
- グアンファシン:α2A-アドレナリン受容体作動薬で、前頭前野の機能を改善します。
薬物療法は、適切な診断と処方のもとで行われることが重要です。副作用や効果を慎重に評価しながら、個人に最適な薬剤と用量を調整していきます。
非薬物療法(心理社会的治療)
非薬物療法には、以下のようなアプローチがあります:
- 心理教育:ADHDについての正しい知識を得ることで、自己理解を深め、適切な対処法を学びます。
- 認知行動療法:非機能的な思考パターンや行動パターンを認識し、より適応的なものに変えていくことを目指します。
- コーチング:日常生活の課題に対する具体的な対処法やスキルを身につけるサポートを行います。
- 環境調整:家庭や職場、学校などの環境を、ADHDの特性に合わせて調整します。
- ソーシャルスキルトレーニング:対人関係のスキルを向上させるためのトレーニングを行います。
非薬物療法は、薬物療法と併用することでより効果的になることが多いです。特に大人のADHDでは、長年にわたって形成された不適応的な対処パターンを変えていくために、心理社会的アプローチが重要となります。
デジタル治療用アプリの登場
最近の新しい治療法として、デジタル治療用アプリも登場しています。2025年2月には、小児のADHD患者を対象としたデジタル治療用アプリ「ENDEAVORRIDE(エンデバーライド)®」が日本で製造販売承認を取得しました。
このアプリは、認知機能において重要な役割を果たすとされる脳の前頭前野を活性化するように設計されており、患者さんごとに最適化された二重課題を行うことで大脳皮質を刺激し、不注意、多動性、および衝動性を改善するように促します。
このように、薬物療法だけでなく、心理社会的治療やデジタル治療など、多様な治療選択肢が提供されることで、より多くのADHD患者の症状改善や治療満足度の向上につながることが期待されています。
ADHDの治療は、一人ひとりの症状や生活状況、ニーズに合わせてカスタマイズされることが重要です。「これさえすれば良い」という万能の治療法はなく、様々なアプローチを組み合わせながら、最適な方法を見つけていくプロセスが必要です。
私たちシモキタよあけ心療内科では、患者さん一人ひとりに合わせた治療プランを提案しています。ADHDの特性で困っていることがあれば、ぜひ専門医に相談してみてください。
ADHDの人への接し方と支援
ADHDの人が抱える困難は、周囲の理解と適切な支援によって大きく軽減することができます。家族や友人、職場の同僚など、身近な人たちの接し方が重要です。
ADHDの特性を「個性」として尊重しながら、必要なサポートを提供することが、本人の自己肯定感を高め、能力を発揮するための鍵となります。
子どものADHDへの接し方
子どものADHDに対しては、以下のような接し方が効果的です:
- 明確で簡潔な指示:一度に複数の指示を出すのではなく、一つずつ簡潔に伝えます。
- 視覚的な手がかり:言葉だけでなく、絵や図、チェックリストなどの視覚的な手がかりを活用します。
- 構造化された環境:予測可能な日課や明確なルールを設け、安心できる環境を作ります。
- 小さな成功体験:達成可能な小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねることで自己肯定感を育みます。
- ポジティブな強化:望ましい行動に対して具体的に褒め、肯定的なフィードバックを与えます。
- 興味を活かす:本人の興味や関心を活かした学習方法を取り入れます。
子どものADHDへの対応では、叱責や罰よりも、肯定的なアプローチが効果的です。「できないこと」に焦点を当てるのではなく、「できること」や「強み」に注目することが大切です。
大人のADHDへの接し方
大人のADHDに対しては、以下のような接し方が効果的です:
- 理解と共感:ADHDの特性を理解し、本人の困難に共感的な態度で接します。
- 明確なコミュニケーション:曖昧な表現を避け、具体的かつ明確に伝えます。
- メモや記録の活用:重要な情報は口頭だけでなく、メールやメモなど記録に残る形で伝えます。
- 強みを活かす環境:創造性や機転の良さなど、ADHDの強みを活かせる役割や環境を提供します。
- 適切なフィードバック:具体的かつ建設的なフィードバックを提供します。
- 柔軟性:働き方や学び方に柔軟性を持たせ、個人に合った方法を認めます。
大人のADHDへの対応では、本人の自律性を尊重しながら、必要なサポートを提供することが重要です。「怠けている」「努力が足りない」などの誤解や偏見を持たず、特性に対する理解を深めることが大切です。
ADHDの強みを活かす
ADHDには困難だけでなく、強みもたくさんあります。これらの強みを認識し、活かすことが重要です:
- 創造性と発想力:多方向に注意が向くことで、独創的なアイデアが生まれることがあります。
- エネルギッシュさ:高いエネルギーレベルを活かして、情熱的に取り組むことができます。
- 柔軟性:状況の変化に素早く対応できる柔軟性を持っています。
- 直感力:直感的な判断が優れていることがあります。
- 共感性:自身の経験から、他者の困難に対する深い共感を持つことがあります。
- 危機対応力:緊急時や危機的状況で力を発揮することがあります。
ADHDの特性は、適切な環境や役割によっては大きな強みとなります。例えば、創造性が求められる職業や、変化の多い環境では、ADHDの特性が活きることがあります。
ADHDの人の可能性を最大限に引き出すためには、その人の特性を理解し、強みを活かせる環境を整えることが大切です。
あなたの周りにいるADHDの人の強みは何でしょうか?その強みを活かせる環境や役割を考えてみてください。
まとめ:ADHDの理解と共生に向けて
本記事では、ADHDの特徴と診断基準、子どもと大人の違い、治療法、接し方について詳しく解説してきました。ここで重要なポイントをまとめておきましょう。
- ADHDは「注意欠如・多動症」と呼ばれる発達障害の一種で、不注意、多動性、衝動性を主な特徴とします。
- 子どもの約5%、大人の約2.1%(50人に1人程度)がADHDと言われています。
- ADHDの診断には、症状が12歳以前から始まり、複数の環境で見られ、日常生活に支障をきたしていることなどの条件があります。
- 子どものADHDでは多動性が目立ちやすく、大人のADHDでは不注意の症状が前面に出ることが多いです。
- 治療には薬物療法と非薬物療法(心理社会的治療)があり、個人に合わせた包括的なアプローチが効果的です。
- ADHDの人への接し方では、特性を理解し、強みを活かせる環境を整えることが重要です。
ADHDは「障害」というよりも「脳の多様性」の一つと捉えることができます。その特性によって困難を抱えることもありますが、適切な理解と支援があれば、ADHDの人も自分らしく能力を発揮することができます。
私たち精神科医が目指すのは、ADHDの方が自分の特性を理解し、それを活かしながら充実した人生を送れるようサポートすることです。そのためには、社会全体でADHDに対する理解を深め、多様性を尊重する環境を作っていくことが大切です。
もし、ご自身やご家族にADHDの可能性を感じたら、一人で悩まず、専門医に相談することをお勧めします。適切な診断と支援によって、生活の質は大きく向上する可能性があります。
シモキタよあけ心療内科では、ADHDをはじめとする発達障害の診断・治療を行っています。専門的な知識と経験を持った医師が、一人ひとりに合わせた治療プランを提案いたします。お気軽にご相談ください。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医