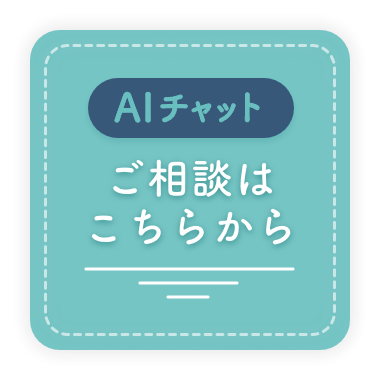2025年8月05日

不眠症とはどのような状態なのか
不眠症は、十分な睡眠時間と環境があるにもかかわらず、寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、早朝に目覚めてしまう、熟睡感が得られないなどの症状が週に3日以上あり、これらが3ヶ月以上続く状態です。
不眠症には大きく分けて4つのタイプがあります。寝つきが悪い「入眠障害」、眠りが浅く睡眠中に何度も目が覚める「中途覚醒」、予定より2時間以上早く目覚めてしまう「早朝覚醒」、そして十分な時間眠っているのに熟睡感がない「熟眠障害」です。
不眠症の原因は複数の要因が重なって発症することが特徴です。環境要因としては室温や騒音、光の漏れなどが、身体的要因ではホルモンバランスの乱れや慢性的な痛み、夜間頻尿などが挙げられます。心理的要因としては仕事や人間関係のストレス、将来への不安、うつ状態なども大きく影響します。
また、不規則な睡眠時間や夜更かし、運動不足、就寝前のカフェイン摂取やスマートフォン使用といった生活習慣も睡眠の質を低下させる原因となります。さらに、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、不眠症以外の睡眠に関わる疾患が原因となることもあります。
不眠症の診療科選びで迷ったらまず何科に行くべきか
不眠症の症状があり病院を受診しようと考えた場合、どの診療科を選べばよいのか迷う方は多いでしょう。結論から言うと、不眠症の原因によって適切な診療科は異なります。
ストレスや不安、うつ状態など心理的な要因が強い場合は、心療内科や精神科を受診するのが適切です。一方、生活習慣の乱れや自律神経の乱れが原因と思われる場合は、まずはかかりつけ医に相談してみてもよいでしょう。
不眠症の症状が長期間続いている場合や、他の睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群など)の可能性がある場合は、睡眠専門の医療機関を受診することも選択肢となります。
どこに行けばよいか本当に分からない場合は、まずかかりつけ医に相談するのが良いでしょう。かかりつけ医が症状を評価し、必要に応じて適切な専門医を紹介してくれます。
では、それぞれの診療科での不眠症治療の特徴について詳しく見ていきましょう。
内科での不眠症診療の特徴と適している症状
内科は風邪や腹痛など、日常的な身体の不調に対応する総合的な診療科です。不眠症に関しても、特に身体的な原因が疑われる場合は内科を受診するのが適切です。
内科での不眠症診療の特徴は、身体的な側面からのアプローチです。高血圧や糖尿病、甲状腺疾患、更年期障害といった身体疾患が不眠の原因となっていることがあります。例えば、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される「甲状腺機能亢進症」では、代謝が活発になりすぎて、動悸や息切れと共に不眠の症状が現れることがあります。
内科医は問診や身体診察、血液検査などを通して、身体的な面から不眠症の原因を探ります。生活習慣の改善指導や、必要に応じて睡眠薬の処方を行います。症状が重い場合や、専門的な治療が必要と判断された場合は、精神科や睡眠専門医療機関へ紹介されることもあります。
内科受診が適している不眠症状としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 身体的な不調(頭痛、めまい、動悸など)と共に不眠がある
- 生活習慣の乱れ(不規則な睡眠、運動不足など)が原因と思われる
- 高血圧や糖尿病などの持病がある
- 更年期障害に伴う不眠
- 軽度から中等度の不眠症状
内科は全国的に数が多く、アクセスしやすいという利点があります。不眠症状が比較的軽度で、身体的な原因が疑われる場合は、まず内科を受診するのが良いでしょう。
精神科・心療内科での不眠症診療の特徴と適している症状
精神科や心療内科は、うつ病や不安障害など、心の問題を専門的に扱う診療科です。不眠症の中でも、特に心理的な要因が強い場合は、これらの診療科を受診するのが適切です。
「精神科を受診するのは恥ずかしい」と感じる方もいるかもしれませんが、そのような心配は無用です。精神科や心療内科を受診することは、決して特別なことではありません。むしろ、自分の心と体の健康を大切にする前向きな行動と言えるでしょう。
精神科・心療内科での不眠症診療の特徴は、患者さんとの丁寧な対話を通して、不眠症の背景にある心理的な要因を探っていくことです。ストレスや不安、緊張など、さまざまな心理的な要因によって不眠症が引き起こされることがあります。また、うつ病などの精神疾患に伴い、不眠の症状が現れることも少なくありません。
治療としては、薬物療法とともに、患者さん自身がストレスとの向き合い方やリラックスする方法を身につけるためのサポートも行われます。認知行動療法など、睡眠に関する考え方や行動パターンを変えていく心理療法が効果的なケースもあります。
精神科・心療内科受診が適している不眠症状としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 強いストレスや不安を感じている
- 気分の落ち込みや意欲の低下がある
- 考え事が多く、頭が冴えて眠れない
- 不眠に対する不安や恐怖感が強い
- 睡眠薬を長期間服用している
- 過去にうつ病や不安障害などの診断を受けたことがある
精神科と心療内科は、扱う疾患に重なる部分が多いですが、一般的に心療内科は身体症状を伴う心の問題に、精神科はより幅広い精神疾患に対応しています。どちらを選ぶか迷った場合は、まず心療内科を受診し、必要に応じて精神科を紹介してもらうという方法もあります。
睡眠専門医療機関での診療の特徴
睡眠に特化した専門的な診療科です。不眠症をはじめ、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)、むずむず脚症候群、特発性過眠症、ナルコレプシーなど、さまざまな睡眠障害の診断・治療にあたっています。
他の診療科を受診してもなかなか不眠症が改善しない場合や、自分の症状が何科を受診すべきかわからない場合には、睡眠科の受診を検討してみましょう。睡眠科には、睡眠に関する専門的な知識と技術を持った医師やスタッフがおり、専門性の高い医療を提供しています。
不眠症の診療科選びのポイント
不眠症で悩んでいる場合、どの診療科を選ぶべきか迷うことがあります。ここでは、適切な診療科を選ぶためのポイントをご紹介します。
まず、自分の不眠症状と考えられる原因を整理しましょう。身体的な症状が強い場合は内科、心理的な要因が強い場合は精神科や心療内科、複雑な睡眠の問題がある場合は睡眠科が適しています。
次に、以下のポイントを参考に診療科を選びましょう。
- 症状の性質と強さ:身体的な症状(頭痛、めまい、動悸など)が強い場合は内科、心理的な症状(不安、抑うつ、ストレスなど)が強い場合は精神科・心療内科が適しています。
- 併存する症状や疾患:高血圧や糖尿病などの身体疾患がある場合は内科、うつ病や不安障害などの精神疾患がある場合は精神科・心療内科が適しています。
- 過去の治療歴:過去に特定の診療科で良い結果が得られた場合は、同じ診療科を選ぶとよいでしょう。
- アクセスのしやすさ:通院のしやすさも重要な要素です。定期的に通院する必要があるため、自宅や職場から通いやすい医療機関を選びましょう。
- 医師との相性:特に精神科・心療内科では、医師との相性が治療効果に影響することがあります。初診で合わないと感じた場合は、別の医師や医療機関を検討することも大切です。
不眠症の治療は一度きりではなく、継続的な通院が必要になることが多いです。そのため、自分に合った診療科・医療機関を選ぶことが、治療を続けるモチベーションにもつながります。
どの診療科を選べばよいか本当に迷った場合は、まずかかりつけ医に相談するのがおすすめです。かかりつけ医が症状を評価し、適切な診療科を紹介してくれるでしょう。
不眠症の治療方法と経過
不眠症の治療は、症状の原因や重症度によって異なりますが、一般的には以下のような流れで進められます。
まず、医師の指導のもとで生活習慣の改善や睡眠環境の見直しを行います。これを「睡眠衛生指導」と呼びます。具体的には、規則正しい睡眠スケジュールの確立、就寝前のカフェインやアルコールの摂取を避ける、寝室の環境(温度、光、音など)を整える、就寝前のリラックス法を取り入れるなどの指導が行われます。
睡眠衛生指導だけで改善が見られない場合は、薬物療法が検討されます。不眠症のタイプや患者さんの状態に応じて、適切な睡眠薬が処方されます。現在、さまざまなタイプの睡眠薬が登場しており、脳の抑制系の働きを促すもの、脳内の眠りホルモンの作用を助けるもの、脳の覚醒系の働きを抑えるものなどがあります。
また、うつ病や不安症など、不眠症以外の病気を持っている場合は、その病気の治療も並行して行われます。例えば、うつ病が原因で不眠が生じている場合は、抗うつ薬の処方や心理療法が行われることがあります。
効果の有無や患者さんの状況を考慮しつつ、認知行動療法などの非薬物療法を組み合わせることもあります。不眠症に対する認知行動療法は、睡眠に関する誤った考え方や行動パターンを修正し、健康的な睡眠習慣を身につけるための治療法です。
治療が効いて症状が改善した場合は、治療をどの程度の期間続けるべきか患者さんと話し合い、治療ゴールを設定します。また、改善度に応じて薬の減量や中止を検討していきます。
不眠症の経過は個人差がありますが、適切な治療を受けることで多くの場合改善が見られます。ただし、自己判断で治療を中断すると症状が再発することがあるため、医師の指示に従って治療を続けることが大切です。
不眠症で病院に行くタイミング
不眠症の症状があっても、「これくらいなら大丈夫だろう」と思って病院受診を先延ばしにしてしまう方は少なくありません。しかし、不眠症を放置すると、日中のパフォーマンス低下だけでなく、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。
では、どのようなタイミングで病院を受診すべきなのでしょうか。以下のような場合は、医療機関への受診を検討しましょう。
- 不眠の症状が1ヶ月以上続いている
- 不眠のために日中の活動に支障が出ている(集中力低下、疲労感、イライラなど)
- 市販の睡眠改善薬を使用しても効果がない
- 睡眠薬を長期間服用している
- いびきや呼吸停止、脚のむずむず感など、特殊な症状を伴う
- 不眠に対する不安や恐怖感が強い
特に、不眠症状が長期間(3ヶ月以上)続く「慢性不眠症」の場合は、専門的な治療が必要となることが多いです。慢性不眠症は、単に眠れないという問題だけでなく、日中の活動や生活の質全体に大きな影響を与えます。
また、高齢者や持病のある方は、不眠症が他の健康問題を悪化させる可能性があるため、早めの受診が望ましいでしょう。
不眠症の治療は、早期に開始するほど効果的であることが多いです。「様子を見よう」と思っているうちに症状が悪化し、治療が長期化してしまうケースもあります。不眠でお悩みの方は、ぜひ早めに医療機関を受診することをおすすめします。
まとめ:不眠症の適切な診療科選びと治療
不眠症で病院に行く際の診療科選びについて、詳しく解説してきました。最後に、ポイントをまとめておきましょう。
不眠症の原因は多岐にわたり、それに応じて適切な診療科も異なります。身体的な原因が疑われる場合は内科、心理的な要因が強い場合は精神科や心療内科、複雑な睡眠の問題がある場合は睡眠科が適しています。どの診療科を選べばよいか迷った場合は、まずかかりつけ医に相談するのがおすすめです。
不眠症の治療は、生活習慣の改善や睡眠環境の見直しから始まり、必要に応じて薬物療法や認知行動療法などが組み合わされます。治療は一度きりではなく、継続的な通院が必要になることが多いため、自分に合った診療科・医療機関を選ぶことが大切です。
不眠症状が1ヶ月以上続いている、日中の活動に支障が出ている、市販薬で効果がないなどの場合は、早めに医療機関を受診しましょう。早期の適切な治療が、不眠症の改善への近道となります。
睡眠は私たちの心身の健康を支える重要な要素です。不眠でお悩みの方は、ぜひ専門家に相談し、質の高い睡眠を取り戻してください。
当院シモキタよあけ心療内科では、不眠症をはじめとする様々な精神疾患の診療を行っています。精神科専門医による質の高い医療で、皆さまの心のやすらぎをサポートいたします。不眠でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
詳しい情報や予約方法については、シモキタよあけ心療内科の公式サイトをご覧ください。
著者プロフィール
「シモキタよあけ心療内科 院長 副島正紀」

〜こころに、よあけを〜
【資格・所属学会】
- 日本精神神経学会 精神科専門医
- 日本精神神経学会 精神科指導医
- 精神保健指定医
- 認知症診療医